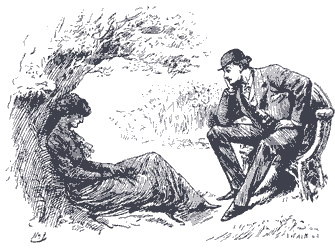
十日は瞬く間に過ぎ去った。パーティを翌日に控えたその日、アーサーに誘われて、午後のお茶に間に合うように館まで散歩することになった。
「一人の方がいいんじゃないのかい?」ぼくはそんなふうに言ってみた。「さぞかしぼくは
「まあ実験のようなものです。
「ぼくの役どころはどうやら、相応しくない人間の実例かな?」
「まさか、そんな」家を出たところで、アーサーは考え込んだ。「レギュラー団員にはそんな役はありませんよ。『頑固親父』? そんなの駄目だ、間に合ってる。『歌う女中』? いや、『ファーストレディ』ならその役と二役できる。『お笑い芸人』? お笑いだな。するとやっぱり『紳士ぶった悪党』しかありませんねえ。もっとも――」値踏みするように横目を使い、「紳士のことにはあンまり詳しくないのでね!」
いたのはミュリエル嬢が一人だけで、伯爵は人に会いに出ていたものの、すぐにぼくらは旧交を温め合った。こかげの四阿ではティーセットが変わらぬ様子で待ち受けていたが、ひとつだけ目を惹いたのは(ミュリエル嬢はまったく当たり前のことだと思っているようだが)、二脚の椅子がぴったり隣り合わせに並べて置かれていたことだった。不思議なことに、ぼくはどちらの椅子も勧めてもらえなかった!
「途中で手紙のことを話していたんだ」アーサーが話し始めた。「ぼくらがスイス旅行をどれだけ楽しんでいるか知りたいというからね。もちろん楽しんでいるということにしなくてはね?」
「それはそうよ」ミュリエル嬢は迷わず同意した。
「確かに台所事情というのは」とぼくは口した。
「――厄介なものですから」ミュリエル嬢が即座にあとを引き取った。「ことにあちこち飛び回っていては、ホテルに台所なんてありませんもの。でもわたしたちのは携帯用ですからね。しかも素敵な革装ケースに入れてしっかりくるんでありますから」
「書き物のことなんか忘れてくれよ」ぼくは言った。「手許にもっと楽しいことがあるんだから。手紙を読むのは楽しいけれど、書くときの苦労は百も承知だからね」
「そういうこともありますね」アーサーが頷いた。「たとえば内気な人が手紙を書かなければならないとき」
「文字に人柄が出るものかしら?」ミュリエル嬢が疑問を口にした。「そりゃね、誰かが――例えばあなたと――しゃべるのを聞けば、その人がどれだけひどく内気なのか判断できるわ! だけど文字で判断できるでしょうか?」
「そうだな、誰かが――例えば君と――すらすら話をしていれば、その人がどれだけひどく内気じゃないかわかるよ――勝気と言ったら言い過ぎにしても! だけどひどく内気でぽつぽつとしか話せない人でも、手紙の文章を見たら流暢に見えるんじゃないかな。二つ目の文章を書くのに三十分かかったかもしれないのに、一つ目の文章のすぐ後ろにあるんだからね!」
「じゃあ手紙だと表現できるはずのことを表現しきれないの?」
「現状の手紙の書き方に不備があるだけだよ。書く人が内気なら、内気だということを表現できなければおかしい。どうして文章のなかで一息ついちゃだめなんだい、話すときにはそうするのに? 空白のままにしておけばいい――一息につき半ページでどうだろう。あるいはとても内気な女の子なら――そんなものが存在するとして――一枚目の便箋に一行書いて――それから真っ白な便箋を二枚挟んで――四枚目の便箋に一行書いたりしてもいい」
「未来が見えます、わたしたち――この賢い坊やとわたしの――」とミュリエル嬢がぼくに声をかけたのは、もちろん会話の仲間に加えようという親切心だ。「――有名人になってるんです――もちろん発明品は今は共有財産になっていてるんですけれど――新しい文章記述書式のおかげです! お願い、もっと発明して」
「そうだな、これも何が何でも必要じゃないかな、何ら意味のない表現の仕方」
「説明希望! そんなに簡単に、まったく意味のないことを表現できるの?」
「本気にされるような意味ではないことを口にするときに、伝えたいとおりに表現できると言いたかったんだ。なにしろ人間というものはうまくできたもので、本気で書いたことを冗談だと受け取られたり、冗談のつもりでも本気に受け取られたりしてしまうんだから! 何はともあれ女性に宛てて書くとそうなるね!」
「そんなに何人も女性宛てに書いたことなんてないくせに!」ミュリエル嬢は椅子にもたれかかったまま空をにらんで考え込んでいるふうだった。「書いてごらんなさいよ」
「いいね」アーサーが言った。「何人くらいに書けばいい? 両手の指で数えられるくらいかな?」
「片手の親指で数えられるくらいよ!」ミュリエル嬢は重々しく答えた。「何ていたずらっ子なのかしら! そうじゃありません?」(と、ぼくの方に魅力的な一瞥をくれた)。
「手に負えないところはあるけれど、きっともう分別もついているよ」ぼくはそう言いながら独り言ちていた。「ブルーノに話しかけるシルヴィーそのものじゃないか!」
「お茶を欲しがってるよ」(いたずらっ子が情報を自ら伝えた。)「明日の素晴らしいパーティのことを考えるだけでくたくただよ!」
「だったら前もって一休みしておかなくちゃね!」ミュリエル嬢はいたわるように答えた。「お茶はまだ淹れてないの。ほら、ちゃんと椅子に座って、なんにも考えないか――わたしのこと考えるか、どっちか好きな方をしておいて!」
「みんな一緒のことじゃないか!」アーサーは愛おしそうな目をして、むにゃむにゃとつぶやいた。そうしているうちにミュリエル嬢はティー・テーブルまで椅子を動かし、お茶を淹れ始めた。「それじゃあいたずらっ子はお茶を待ってるからね、いい子にして、我慢してるんだ!」
「ロンドン新聞を持ってきた方がいい?」ミュリエル嬢がたずねた。「出がけに、テーブルに置いてあるのを見かけたの。何にもないって父は言ってたけれど。ぞっとするような殺人の公判は別だけど!」(そのころ世間の人々は日々興奮に震えて、ロンドン東部にある泥棒のねぐらで起こった刺激的な殺人の詳細をわくわくと見守っていた。)
「怖い話はごめんだな」アーサーが答えた。「でもそこから導かれる教訓は学んだ方がいい――ところが人はそれをしょっちゅうあべこべに解釈してしまうものなんだ!」
「また謎めかすんだから。さあ説明してちょうだい」言葉にしたがい動きながら、「ここに座って教えを請うわ、あなたは第二のガマリエルってとこ! いえ、いいんです」[*1](これはぼくに言った言葉だ。ぼくはミュリエル嬢の椅子を後ろに引こうと立ち上がっていた。)「お気になさらずに。この木と芝生が快適な安楽椅子になりますから。解釈を間違ってばかりの教訓って何かしら?」
アーサーはしばらく何も言わなかった。「何なのかはっきりさせたいな」とゆっくり考え込みながら口を開いた。「君に何か言う前に――君がそのことを考えているんだから」
お世辞のようなことを言うのはアーサーには珍しいことだったので、ミュリエル嬢の頬がうれしさで赤く染まった。「考える材料をくれたのはあなたじゃない」
「真っ先に頭に浮かびがちなのが、ある同胞がやったようなひどくおぞましく残忍なことを読み取ることで、罪の深淵がぼくらの足許に新たに姿を見せたということなんだ。高くて遠く離れた場所から深淵を覗き込んでいるような気になっているんだね」
「何となくわかった。みんなこう思うべきだって言いたいのね――『神さま、私が彼の者たちと違うことを感謝します』――ではなく、『神さま、あなたの恩寵がなければ同じように罪深いであろう私に、お慈悲を』と」」[*2]
「いや」アーサーが言った。「それ以上のことさ」
ミュリエル嬢は目を上げたが、口を挟まず無言のまま待った。
「もっと遡らなくては。その不幸な人と同い年の、別人のことを考えてみるんだ。二人が生まれたころに遡ってみよう――まだ善悪の感情もなかったころに。とにかくそのころは、神の目から見れば二人とも平等だった――」
ミュリエル嬢が頷いた。
「こうして人生を比較している二人の人間のことを考えるに当たって、はっきりとした二つの時期がある。第一の時期には、道徳的責任については、二人とも同じ土台に立脚していたんだ。二人とも善も悪も判断できなかった。第二の時期になると、一人目の人間は――比較のために極端な例えをするけれど――あらゆる尊敬と愛を勝ち取った。その評判は錆びることなく、その名にはそれからも名誉がついて回るだろう。二人目の人間の歴史は単調な犯罪の記録でしかなく、最後にはその国の怒れる法に生命を奪われてしまった。それぞれの場合に、第二の時期を左右することになる原因は何だったのか? 二種類のことが考えられる――ひとつは内部要因、もうひとつは外部要因。この二つは別々に考えなくてはならない――それはそうと、こんなつまんない話ばかりで退屈していないかい?」
「それどころか」ミュリエル嬢が答えた。「面白くて仕方ないわ。こんなふうに一つの問題について議論して――理解できるように分析したり整理したりするのは。問題を論じているふりをしているだけのひどく退屈な本もあることだし。考えが理路整然と組み立てられていないんだもの――『思いついた端から』ってとこ」
「勇気百倍だ」アーサーは嬉しそうな顔をした。「内部要因というのは時間とともに人格を形作る、意思による一連の行為――要するに、これをするかあれをするか選ぶという行為のことだ」
「自由意思の存在を前提とするのかい?」ぼくはその点をはっきりさせようとした。
「さもなければ
「前提とします!」残りの聴衆――アーサーから見れば過半数ということになるのだろう――がはっきりと宣言した。アーサーは話を続けた。
「外部要因とは、周囲の環境だ――ハーバート・スペンサー氏が『適応環境』と呼んでいたものだね。ここではっきりさせておきたいのは、人は自分の選んだ行為に対する責任はあるが、環境に対する責任はないということだ。だからこの二人が、とある状況で同じ誘惑にさらされたときに、同じように抵抗して同じように正しい道を選ぼうとするのであれば、神の目からは二人の立場は同じはずなんだ。一人が神の御心にかなったのなら、もう一人の場合もそうだし、一人が御心を損じたのなら、もう一人も損じるだろうね」
「その通りだと思う。よくわかるわ」ミュリエル嬢が相槌を打った。
「それなのに、それぞれの環境が原因で、一人は誘惑に大きな勝利をおさめ、もう一人は真っ暗な罪の深淵に落ちてしまうんだ」
「だけど二人とも神の目から見ればまったく同じように罪を犯していると言わなかった?」
「さもなけりゃ、完全なる神の裁きを疑わざるを得ないよ。それよりもう一ついいかな、それでもっとはっきり説明できると思う。一人は上流階級の人間――もう一人は泥棒の常習犯だとしよう。上流階級の人間が些細な不正行為に手を染める機会を得たとする――それも不正が絶対に見つからないと確信できるような行為で――不正に手を染めずにいることも極めて簡単な行為で――罪であることが明らかな行為だ。もう一人は恐ろしい犯罪に手を染める機会を得たとする――誰もが大犯罪だと見なすような犯罪だけど――罪を犯そうとするどうしようもないほどの衝動に押しつぶされているんだ――もちろん完全にどうしようもないわけじゃなく、あらゆる責任をくじくほどではない。こうした場合、第二の人間が誘惑に抵抗するには第一の人間の何倍もの力がいると考えてみよう。そしてまた、二人とも誘惑に負けてしまった場合を考えてみれば――第二の人間は、神の目から見れば、もう一人ほど罪がありはしないと思うんだ」
ミュリエル嬢が長々と息を洩らした。「善悪の概念がひっくり返ってしまうわね――初めのうちは! だって殺人事件の裁判のとき、裁判所で一番罪深くない人間が殺人犯かもしれないってことでしょう。しかも公正を欠いた発言をするという誘惑に負けて、犯人を裁いた判事は、もしかしたら犯罪者が生涯に犯した罪より重い罪を犯したかもしれないってことじゃない!」
「まさしくそうだよ」アーサーが断言した。「逆説みたいに聞こえるのはわかる。でも神の目から見れば、何の苦もなく抗えるようなつまらない誘惑に負けるなんて、計り知れない重罪に違いないと思わないか。しかも故意に、神の法の光に照らされている状態でそんなことをするなんて。どう懺悔してもそんな罪をあがなえるとは思えないだろう?」
「その考え方は認めざるを得ないな」ぼくは言った。「だけどそうなると、世界中にどれだけ罪が広がっていることになるんだろう!」
「そうなるの?」ミュリエル嬢が心配そうにたずねた。
「いや、とんでもない!」という力強い答えが返ってきた。「むしろ世界の歴史を覆っている雲がすっきりと払いのけられたような気がする。こうやってものを見ることで初めてすっきりしたのは忘れもしない、野原に向かいながらテニスンの一節を口ずさんでいたときのことだ。『悪き心は見あたらず!』 もしかしたら人類が犯した現実の罪は、ぼくが思っているほど無限ではないのではないだろうか――ぼくが絶望的な罪の淵に沈んでいるものとばかり考えていたいくつものことは、もしかしたら神の目から見ればそれほどの罪ではないのではないだろうか、という考えは――言葉では表現できないほど甘美なものだった! いったんそう考え始めてしまえば、人生がいっそう輝かしく素晴らしいものに見えたよ! 『草むらのエメラルドがずっと輝きを増し、海に溶けるサファイアがずっと澄んで見える!』[*3]」と締めくくったときには、声は震え、目には涙がたまっていた。
ミュリエル嬢は手で顔を覆い、しばらくのあいだ何も言わなかった。「素敵な考え」と口にして、ようやく顔を上げた。「ありがとう――アーサー、こんな素敵な考えを教えてくれて!」
そうこうしているうちに伯爵が戻ってきてお茶に加わり、ありがたくない報せを持ち込んだ。目と鼻の先の港町で熱病が発生したという――たいへん悪性のもので、始まりはわずか一日か二日前に過ぎないと思われるのに、すでに十人以上が倒れ、そのうちの二、三人はかなり危険な状態だということだった。
アーサーがしきりと質問を――その出来事に極めて高い科学的関心を持ったのに違いなく――質問をするのだが、地元の医者と会っていたというのに伯爵はこまごまとした専門的なことにはほとんど答えられなかった。それでもどうやら、ほぼ未知の――少なくとも今世紀になってからは知られていない病気のようだ。そうはいっても、『黒死病』として歴史に記録されている病気と同じものだと判明する可能性だってある――恐ろしい感染力に、とてつもない速さによる蔓延。「それでも明日のパーティに支障はないよ」伯爵はそう締めくくった。「招待している人たちのなかに、感染地域に住んでる人はいないからね。あそこは漁師町だ。何も心配いらない」
アーサーは帰宅するあいだも黙り込んでいた。宿に着くとすぐに医学的な調べものに取りかかった。つい今しがた耳にしたばかりの気がかりな疫病についてだった。
"Sylvie And Bruno Concluded" Lewis Carroll -- Chapter VIII 'In A Shady Place' の全訳です。
Ver.1 03/05/20
Ver.2 03/10/08
Ver.3 03/11/06
Ver.4 11/02/16
[註釈]
▼*註1 [ガマリエル]。「使徒行伝」第22章第3節。
そこで彼は言葉をついで言った、「わたしはキリキヤのタルソで生れたユダヤ人であるが、この都で育てられ、ガマリエルのひざもとで先祖伝来の律法について、きびしい薫陶を受け、今日の皆さんと同じく神に対して熱心な者であった。(口語訳)。[↑]
▼*註2 [あなたの恩寵がなければ] 原文「God, be merciful to me also, who might be, but for Thy grace, a sinner as vile as he!」。John Bradford(1510-1555)の言葉 "But for the grace of God, there goes John Bradford."(神の恩寵なかりせば、ジョン・ブラッドフォードもかくなるらん)が有名。[↑]
▼*註3 [草むらのエメラルド……] 初めに「口ずさんでいた」一節は、Tennyson「The Two Voices」より。455「There seemed no room for sense of wrong(There seem'd no room for sense of wrong)」(森には歌が満ちあふれ、/悪き心は見あたらず。)
台詞末尾の「草むらのエメラルドが……」はTennyson『Maud』PARTI. XVIII. 6.より。「A livelier emerald twinkles in the grass, A purer sapphire melts into the sea」。
テニスン『二つの声』本文全訳は→こちら。