tortil。
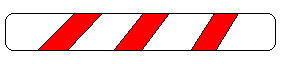 男爵冠のデザインを図案化したもの。[↑]
男爵冠のデザインを図案化したもの。[↑]先ほどの物語から七日後のことである。宵の五時ごろ、二人の馭者の駆る四頭立ての馬車が、ナンシー(Nancy)とメス(Metz)の間に位置する小都市ポン=タ=ムソン(Pont-à-Mousson)を出発した。今しがた宿場で馬を替えたばかりである。女将が戸口で愛嬌を振りまき遅入りの旅客を引き留めようとしたが、馬車はパリへの道を急いでいた。[*1]
四頭の馬が重い車体を曳いて辻に消えると、馬替えの最中は馬車を取り囲んでいたわらしこもおかみさんも、てんでに身振り口振りを交えながら家路についた。面白がっている者もいれば、驚いている者もいた。
それというのも五十年前に善良王スタニスワフが公国とフランスとの連絡を容易にしようとモーゼル川に橋を架けて以来、このような馬車が橋を渡ったことなどついぞなかった。市の立つ日には、双頭の怪物、踊りを踊る熊、放浪部族と自称する文明国の軽業師やジプシーたちを、ファルスブール(Phalsbourg)から連れてくるアルザスのいっぷう変わった有蓋車さえ、例外ではない。[*2]
であるからして、やんちゃ盛りの子供や口さがない年寄りでなくとも、このけったいな車が通り過ぎるのを見て驚いて立ち止まったとしてもおかしくはない。しかしながら同じ大きさの前輪と後輪に揺られ、丈夫なバネに支えられて走るこの馬車の速度には、目にした人々が思わずこう叫んでしまうのも仕方なかろう。
「駅馬車にしちゃあ変わってるな!」
幸か不幸か現物を目にしていない読者諸氏のために、馬車の全容を明らかにしておこう。
まずは本体部分――という言い方をするのは、二輪馬車のようなものの後ろにこの部分がついているからで――この本体部分は水色に塗られ、扉の真ん中には男爵位を示すねじり巻き模様を戴くようにして、趣味のいいJとBの組み文字が象られていた。[*3]
窓が二つ――扉についた窓ではなく純然たる窓のことだが、白モスリンのカーテンを掛けた窓が二つあり、そこから車内に光が入るようになっていた。ただしこの窓、凡俗の目のほとんど届かぬ本体前部に開いて二輪馬車に通じていた。窓には鉄格子が嵌められていたので、本体にいる人物が何者であれその人物と会話をすることが出来たし、こうした用心がなければとても安心しては出来ないようなことも――即ち、カーテンの掛けられた窓ガラスにもたれることも出来た。
この車輛後部こそが奇妙な馬車の主要部分であるらしい。長さ八ピエ、幅六ピエ、陽射しの入口はその二つの窓のみ、空気の出入口は丸屋根に開いたガラスの嵌った換気口のみであった。そして奇妙な特徴の締めくくりに通行人の目に映っていたのが、少なくとも屋根からたっぷり一ピエははみ出した金属管である。もくもくと吐き出された青い煙が、白い柱となって立ち上り、運び去られる馬車を追う空の波となって広がっていた。[*4]
今日であればこうした特徴も、新しい何かの発明だと思われただけで終わっていただろう。技師が蒸気の力と馬の力を的確に組み合わせたのに違いない、と。
前述した通り馬車は四頭の馬と二人の馭者に曳かれていたが、その車体の後ろには馬が一頭だけ繋索一本で後部車輛に繋がれていた、ともなればこれが新発明らしき可能性はますます強まる。この馬には、小さく弓形の頭部、細長い脚、引き締まった胸、豊かな鬣に燃えるような尾といった、紛う方なきアラブ馬の特徴が備わっていた。鞍を置かれているところから考えて、このノアの方舟に閉じ込められた旅人の誰かが、時折り気晴らしをして、それほどの速度では走れない馬車のそばをギャロップで駆けているのだろう。
ポン=タ=ムソンで手綱を相棒に預けた馭者は馬車賃に加えて二倍の酒手を受け取っていた。モスリンのカーテンが本体前部を閉ざしていたのと同じように、革カーテンが二輪馬車の前部をぴしゃりと閉ざしている。白く逞しい手がその革カーテンの隙間から滑り出て、馬車賃を渡していた。
驚いた馭者は帽子を取って礼を言った。
「こいつぁすまんね、旦那」
よく通る声がドイツ語で応じた。ナンシー近郊にはもうドイツ語を話す者はいないがまだ言葉は通じた。
「Schnel! schneller!」
フランス語にすればこうなる。
「急ぐんだ! もっと急いでくれ!」
馭者はたいていの言語を理解できる。或る金属的な響きの言葉が添えてあれば。馭者といった手合いは――旅人なら先刻ご承知の通り――その金属音が大好きなのである。故に二人の新しい馭者は、急いで出発するために出来る限りのことをした。そして馬の脚の力より馭者の腕の力をたっぷり使った後でようやく、へとへとになりながら、常識的な速さであるトロットに抑えてもよいと認めることが出来たのである。その証拠に、今現在は明らかに一時間で二里半か三里の速度で走っているところであった。
七時頃にはサン=ミエル(Saint-Mihiel)で馬を替えていた。先ほどの手がカーテンから覗いて走破した分の支払いを済ませ、先ほどの声が同じ指示(recommandation)を聞かせた。[*5]
言うまでもなくこの奇妙な馬車はポン=タ=ムソンの時と同じく人々の好奇心をかき立てた。夜も近づきいっそう幻想的に見えたのもそれを後押しした。
サン=ミエルを過ぎれば山道だ。そこから先は並足で走るしかない。四分の一里ほど進むのに半時間かかる。
坂を登りきったところで馭者は車を停めて馬を休ませたので、二輪馬車の乗客たちが革のカーテンを開ければ広大な景色を見晴らせたやもしれぬが、やんぬるかな既に夕靄が降り始めていた。
午後の三時まではからりとした暑さだったが、夜にかけてうだるように蒸して来た。南の空に広がる白い雲が、つけ狙うように馬車を追いかけ、バル=ル=デュックに着く前に捕まえようとしていたため、大事を取ってバル=ル=デュックで夜を過ごした方がいいと馭者は訴えていた。
片や山の斜面、片や断崖に挟み込まれた小径の下の谷底には、ムーズ川が蛇行していた。半里にもわたる急な坂道を降りるには、並足以上の速さでは危険すぎる。そこで馭者たちは速度を抑えて慎重に馬車の操縦を再開した。
雲は歩みを止めず、荒らかに、大地を薙ぐかと思われるほど低くなるにつれ、地面から立ちのぼる靄が露となって広がっていた。つまり、忌まわしい白い魔物が、戦に臨む軍艦のように、風下に居坐ろうとしていた青鼠色の雲を蹴散らしているのが見えた。
やがて雲は潮が満ちるように見る見るうちに空を覆い、残されていた日脚も隠されてしまった。薄暗い光がかろうじて地上にこぼれ、風がなくとも揺れ続ける木の葉が黒ずんだ色を纏った。それは太陽と入れ替わりに訪れる闇という下塗りの色だった。
不意に稲光が雲間を駆け巡り、空が火によって甲羅状にひび割れ、怯えた目には地獄の底のように燃えさかる果てしない天空の底さえ見えたような気がした。
それと同時に木から木へと飛び渡って道を横切る森の端までたどり着いていた稲妻が、文字通り大地を揺るがし、巨大な雲を悍馬のように走らせた。
馬車はといえば煙突から煙を吐き出したまま走り続けていた。もっとも、初めこそ黒っぽかった煙は薄くなり乳白色に変わっていた。
そのうちに空がわなないたように暗くなった。すると屋根の換気口が赤い光に染まり、光はそのまま消えずにいた。外の嵐とは無縁な室内の乗客が、取り組んでいる作業を妨げられぬよう、夜に備えたのだ。
馬車は今なお山上だった。雷鳴がさらに激しい音をばりばりと轟かせて雲間から雨を落とした時も、まだ斜面を降り始めてはいなかった。初めのうちこそ落ちて来たのは大粒の滴であったが、やがて天から放たれた矢のように鋭くしのつく雨がほとばしった。
馭者たちが何やら話し合っているようだ。馬車が止まった。
「おい!」先ほどの人物が声をかけたが、今度は滑らかなフランス語であった。「いったいどうしたんだ?」
「このまま進むべきかどうか考えていたんでさ」
「それを考えるのはお前たちではなく俺じゃないのか? 進め!」
その声の抗いがたい響きに、馭者は命令通り馬車を出し、坂道を進み始めた。
「それでいい!」
わずかに開いた革のカーテンが、すぐに乗客と二輪馬車の間を元通り遮った。
だが道は降り注ぐ豪雨でぐしょぐしょにぬかるみ、俄に滑りやすくなったため、馬が前に進もうとしなかった。
「旦那」手綱を取っていた馭者が声をかけた。「これ以上は進めませんや」
「何故だ?」既にお馴染みの声がたずねた。
「馬が進まんのです。滑っちまって」
「宿場までどのくらいだ?」
「はあ! けっこうあります。四里ってとこで」
「では馬に銀の蹄鉄をつけるがよい。それで進める」そう言ってカーテンを開け、六リーヴル=エキュ銀貨四枚を握らせた。
「こいつはどうも」馭者は大きな手で銀貨を受け取り、ゆったりした革靴の中に滑り落とした。
「旦那の声がしたようだが?」もう一人の馭者が、銀貨の落ちるじゃらじゃらした音を聞きつけて、面白そうなやり取りに乗り遅れまいとした。
「ああ。進めとさ」
「何か問題でもあるのか?」乗客の声は穏やかだが険しく、この点に関しては如何なる反論も受けつけまい。
「いや旦那、あっしにはねぇよ。馬でさ。見ねぇ。梃子でも動かねえって面だ」
「拍車を掛ければよいではないか」
「旦那! 腹に拍車を蹴り込んだところで、ぴくりとも動きやしませんぜ。あっしの言うことに嘘があれば、天罰を喰らったって……」
馭者の暴言は言いも終わらぬうちにとてつもない雷の音と光に断ち切られた。
「とんでもねえ天気だ。ありゃ! 旦那、見なせえ……馬車が勝手に動いてやがる。五分もすりゃあ出したくもない速さになりますぜ。畜生! ひとりでに進んでやがる!」
なるほど重い車体に押されて持ちこたえきれなくなった馬は脚を踏ん張ることも出来ず、重みを増してゆく馬車の車輪がそのうち猛回転を始め、馬車はぐんぐんと前に進んでいた。
馬が痛がって暴れ、乗客たちも暗い坂をすっ飛んでゆく。このまま行けばその先は崖だ。
先ほどまでとは違い、乗客が声だけではなく顔も出した。
「阿呆め! 殺す気か! 左に手綱を取れ! 左だ!」
「いや、旦那! もとよりそのつもりで!」怯えた馭者が手綱を締め、再び馬を御そうとしたが、果たせなかった。
「ジョゼフ!」女の声が初めて聞こえた。「ジョゼフ! 助けて! お願い! 聖母さま!」
現に危険はすぐ目の前まで迫っており、聖母への祈りが洩れるのも当然だった。馬車は重みに引きずられたまま制御も利かず、崖に向かって進み続け、馬の一頭はほとんど宙づりになっているようだ。さらに車輪三回転分前に進めば、馬も馬車も馭者もすべて投げ出され、粉々になっていてもおかしくなかったが、その時乗客の男が二輪馬車から轅に飛びつき、馭者の襟首とベルトをつかんで、子供でも持ち上げるように軽々と持ち上げ、脇に放ると、代わりに鞍に飛び乗って手綱を引き締め、ただならぬ声をあげた。
「左だ!」乗客はもう一人の馭者に怒鳴った。「左だ、阿呆! 頭を吹っ飛ばされたいのか?」
この一言が魔法のような効果を上げた。前列の馬二頭を操っていた馭者は、相方の悲鳴に追い立てられるようにしてあり得ないほどの力を振り絞り、馬車に勢いをつけ、乗客の助けを借りながらも、道の真ん中まで馬車を戻した。と、そこから馬車は雷鳴さながらの音を立てて、飛ぶように走り出した。
「急げ!」と乗客が叫ぶ。「速度を落とすな! 緩めようものなら、お前も馬も踏み潰してやる」
ただの脅しではないと直感した馭者は力を込め、馬車は恐ろしい速度で坂を下り続けた。凄まじい音を轟かせ、煙突を燃え上がらせ、声なき叫びをあげながら夜を往くのを見れば、まるでこの世ならざる馬に曳かれた地獄の馬車が嵐に追われているようだった。
だが一難去ってもまだ終わりではなかった。山間にたなびいていた雷雲は、馬に負けぬ速さで滑るようにひた走っていた。時折り乗客が顔を上げた。やはり稲妻が雲を裂くのは気になるようだ。稲光に照らされた顔には、隠そうともしない不安の色が見えた。どうせ神にしか見えぬのだから隠す必要もない。と、そこで――坂が終わっても馬車の勢いは止まらず、平坦な地面を走り続けていたその時であった。空気の急激な移動によって陽電気と陰電気が結びつき、雲が恐ろしい音と共に裂けて雷光と雷鳴を同時に吐き出した。紫色の炎が青くなったかと思うと最後には真っ白になり、馬たちを包み込んだ。後ろの二頭が棒立ちになって、前脚で空を掻き、硫黄臭い空気をごふごふと吸い込んだ。前の二頭は足許の地面が消え失せたかのようにぱたりと倒れた。だが馭者を乗せていた馬がすぐに立ち上がり、衝撃で引綱が切れていることに気づいて、そのまま立ち去ったので、馭者は闇間に見えなくなった。馬車の方はしばらく走り続けてから、雷に打たれた馬の死体にぶつかって止まっていた。[*6]
この間にも車内からは悲痛な女の叫び声が聞こえ続けていた。
滅茶苦茶な状態がしばらく続き、人の生死も定かではない。乗客の男は身体中に触れて変わりがないかを確かめた。
自分は無事だったが、女が気を失っている。
気を失ったのはさほど前のこととは思われない。馬車から洩れていた悲鳴がぱたりとやんでいたからだ。それなのに男が真っ先に助けに向かったのは、悲嘆に暮れた女のところではなかった。
それどころか足を降ろすや馬車後部に駆け寄った。
そこには前述した見事なアラブ馬がいた。怯えて体躯をがくがくと強張らせていたために、毛の一本一本が生き物のように逆立ち、扉が揺れ、取っ手に繋がれた繋索がぴんと張るほどだった。とうとう目が見開かれ、口から泡を吹き始めた。繋がれた綱を千切ろうと努めたものの甲斐なく、嵐に怯えて目を回してしまったのだ。旅人がいつものように口笛を鳴らしながら手を回して尻を撫でると、馬はびくりと跳ねていなないた。主人のこともわからぬらしい。
「まったく。いつもいつも忌々しい馬め」馬車の中からしわがれた声がした。「壁を揺すりおって。呪われてしまうがいい!」
さらに声は大きくなり、アラビア語に変わった。その声には苛立ちと殺気が籠っていた。
「大人しくしていろと言っただろう、この阿呆め!《Nhe goullac hogoud shaked haffrit !》」
「ジェリドを怒らないで下さい、先生」乗客の男は繋索をほどき、馬車後部の車輪に繋ごうとした。「怯えていただけなんです。もっと何でもないことで怖がる人だっているじゃありませんか」
そう言って扉を開け、昇降段を下げて車内に入ると扉を閉めた。
Alexandre Dumas『Joseph Balsamo』Chapitre I「L'Orage」の全訳です。初出『La Presse』紙 1846/06/03号。
Ver.1 07/10/27
Ver.2 12/09/08
Ver.3 14/05/13
[訳者あとがき]
[更新履歴]
・12/09/06 「sans 〜」の訳し方を間違えていたので訂正。「遊び半分の子供や口さがない年寄りでなければ」→「やんちゃ盛りの子供や口さがない年寄りでなくとも」
・12/09/08 「金属的な音楽で語る言葉」というのが「お金」の譬喩だということに気づいていなかったので、この部分を訂正。「御者はたいていの言葉なら理解できた。旅人たちにはよく知られている通りこの民族お気に入りの、あの金属的な響きが含まれた言葉であれば。というわけで二人の新しい御者は出来うる限りの速度を出そうとした。その結果――といっても、それなりの速度で一戦交えることにしぶしぶ従った馬の脚力というよりは、御者の腕力のたまものなのだが――時速二マイル半から三マイル出すことが出来たのである。→「御者はたいていの言語を理解できる。或る金属的な響きの言葉が添えてあれば。御者といった手合いは――旅人なら先刻ご承知の通り――その金属音が大好きなのである。故に二人の新しい御者は、全速力で馬車を走らせる為に出来る限りのことをした。これは馬の脚力というよりは御者の腕力に拠るところが大きいのだが、渋々ながら適切な速度に落としてトロットにしようと決めたのは、一時間で二里半か三里進んだことが明らかになってからのことだった。」
▼14/05/11 第一段落「Huit jours après」を「八日後」→「一週間後」に訂正。
▼馬車を見た子供や年寄りが叫ぶ段落。「ses quatre roues de pareil diamètre」直訳すれば「同じ直径の四つの車輪」ですが、一つ一つの車輪の直径が違うわけはないのだから、ここでは「前輪と後輪が同じ直径」という意味だと思われます。
「avec assez de rapidité pour justifier cette exclamation échappée aux spectateurs :」「観客の歓声に答えるように猛スピードで進んでいた」 → 「この馬車の速度には、目にした人々が思わずこう叫んでしまうのも仕方なかろう」に訂正。
▼「Tout à coup un éclair sillonna la nuée, le ciel se fendit en losanges de feu」の後ろの部分、直訳すれば「空が菱形に割れた」なのですが、稲妻が光った様子をもっとわかりやすく伝えたくて、いろいろ考えた挙句「甲羅状に」としましたが、うまく伝わっているかどうか自信がありません。
▼「je leur enfoncerais la molette dans le ventre, qu'ils ne feraient pas un pas de plus ; 」。「条件法, que 条件法」で、「〜すれば、…だろう」なので、「あっしが腹に拍車を蹴り込まなかったとでも? ぴくりとも動かねぇんでさ。」 → 「腹に拍車を蹴り込んだところで、ぴくりとも動きやしませんぜ。」に訂正。
[註釈]
▼*1. [一週間後]。
作中の日付に従うなら、1770年5月6日の一週間後であり、5月13日(日)ということになる。[↑]
▼*2. [善良王スタニスワフ]。
善良王スタニスワフ。bon roi Stanislas。1704〜1709 ポーランド王、1737〜1766 ロレーヌ公国君主スタニスラス。ポン=タ=ムソンは1766年まではバル公国=ロレーヌ公国領、メスはフランス領であった。1720〜1725のあいだ元王はアルザスのヴィザンブール(ヴァイセンブルク)にいた。[↑]
▼*3. [ねじり巻き模様]。
tortil。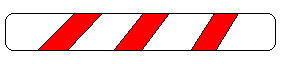 男爵冠のデザインを図案化したもの。[↑]
男爵冠のデザインを図案化したもの。[↑]
▼*4. [八ピエ]。
ピエ。pied。昔の長さの単位。1ピエ=約32センチ。[↑]
▼*5. [七時頃にはサン=ミエル…]。
サン=ミエル(Saint-Mihiel)は、ポン=タ=ムソンから西に約50km離れた町。五時にポン=タ=ムソンを出発した馬車が七時にサン=ミエルについたということは、馬車はおよそ時速25kmで走って来たことになる。ちなみに、トロットに落として、一時間で二里半〜三里なら、時速に直すと10〜12kmである。[↑]
▼*6. [後ろの二頭が…]。「ceux de derrière se cabrèrent en battant [l'air de leurs jambes de devant et en aspirant bruyamment] l'air chargé de soufre ;」。底本には一つ目の「l'air」と二つ目の「l'air」の間が脱落していたため、初出により補った。「後ろの二頭は硫黄臭い空気を掻くように、後脚で立ち上がった。」 → 「後ろの二頭が棒立ちになって、前脚で空を掻き、硫黄臭い空気をごふごふと吸い込んだ。」に訂正。
[↑]