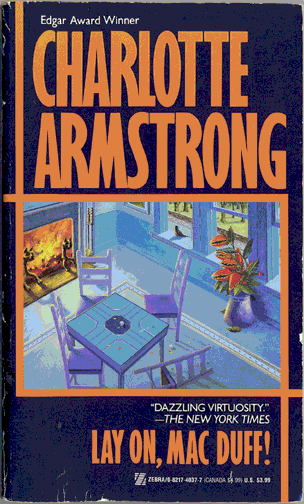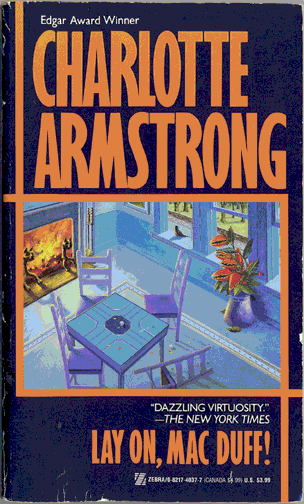
わたしの名前はベッシー・ギボン。二十歳で、もうすぐ結婚する。だけどこのあいだの二月にすべてが起こったときは、まだたったの十九だったのだ。それはニューヨーク・シティ行きの電車に乗るところから始まった。何が起こるかなんて知るはずもなかった。
母は三年前に死んだ。母がいなくなって、父と二人で暮らすのに慣れるには時間がかかった。父はニューヨーク州にある小さな町でメソジストの牧師をしていたが、やはり一年前の秋に死んだ。新任の牧師夫妻と牧師館で暮らしているあいだも、わたしが自活できるようにみんなが手助けしてくれた。でも何の実も結ばなかった。手に職をつけていなかったし、いずれにせよ開くような店も持っていなかった。あの町では、わたしでもできるようなことにお金を払うゆとりなんてなかった。子どものお守りならできたけれど、それは雑役婦の仕事だったし、教会の評判を考えれば雑役婦になれるわけもなかったし、なる気もなかった。
コンパニオンならうまくやれただろうけれど、ベイカーズ・ブリッジの老婦人はコンパニオンなど入り用がないほど元気に独り暮らししていた。残されたのは誰かの妻になることだけだったけれど、肉屋の息子とのけっこういい縁談を断ってしまったので、牧師はあきらめてチャールズ伯父さんに預かってくれと手紙を書いた。
チャールズ・カスカートは母方の伯父だ。父が死んでからすぐに、来ないかという申し出はあったのだけれど、行きたくなんてなかった。今だって行きたくない。でも行くしかないのだ。
チャールズ伯父さんはわたしにとっては神話みたいなものだ。いることは知っていたけれど、会ったことはない。母の葬儀にも父の葬儀にも来なかった。送られてきたのは豪華な花束。かなりの金額も送られてきたので二回とも大助かりだった。知っているのは、世間並に照らして信じられないほどのお金持ちだということだけ。それほど遠くないニューヨーク・シティに住んでいたけれど、今までのわたしにとっては火星に住んでいたのと変わりがなかった。
父が伯父のことを嫌っていたのは気づいていたし、その逆も同じだったのだろう。とにかく、わたしたちの住む厳しくつましい世界から見れば、伯父ははるかに裕福で未知の存在なのだと、まるで腫れ物にさわるような後ろめたい恐れを込めて母が話してくれた。母の父親も牧師だった。伯父は一家の面汚しだったのだという考えに幼いころから囚われていた。しかも伯父の場合には、罪の報いが死ではなくお金だったことが、特殊な事情を生んでいた。
伯父は結婚している。奥さんの名前はリナだ。伯父は五十歳くらいでお金持ちで、家に来ないかと誘ってくれた。それが未来についての全情報だった。あの水曜の晩、高架線を走る列車に揺られて住宅地のあいだを抜け、地下にもぐったところで、目的地が近づいたことを知ったのだ。
わたしは脅えていた。無力だったくせに、無力でいたくないという衝動に駆られていた。哀れな親戚の役で訪れるのはごめんだった。事実はそのとおりだったくせに。田舎びてみすぼらしくてびくびくしていたけれど、仕事を見つけて自活するつもりだったし、具体的な計画を起こそうとしてきた。けれど実際には夢のような話だった。ニューヨークで仕事を見つけようとするのがいったいどんなことなのか、少しも考えていなかったのだ。汗ばんだ手を手袋の中に潜ませたまま、尻込みもせず体裁もつくろわずに、そうしようと決めていたとおり不器用に押し黙っていようと決意した。
興奮していたわたしは、元気をふりしぼって薄暗い丸天井のホームに降り立った。赤帽がスーツケースを運びに来た。迎えが来ているはずだと伝えると、すぐにスーツケースをつかみ上げて先に立ってスロープを上がり始めたので、わたしもすぐに追いかけた。降りる駅を間違えていないことはすぐにわかった。待ち人の顔を探す人たちが見える。赤帽が立ち止まってこちらを見たけれど、わたしはどうすることもできずにあたりを見回して、声を張り上げようかと思っていた。
男の声がした。「エリザベス・ギボンさん?」
「わたしです」ちゃんと連絡が行っていたのだとほっとするあまりよく見えなかったけれど、誰だか知らぬが伯父でないことはわかった。若すぎる。
「ヒュー・ミラーといいます。カスカートさんから頼まれたんですよ。タクシーを拾いましょう」彼がわたしの手を取ると、赤帽はあっというまに別の方角に向かった。
なんとか元気をふりしぼった。「ごめんなさい、でもどちらさまでしたっけ?」
「おっと失礼」困っているようだった。「ええと……何て言えばいいのかな……伯父さんの友人のところで働いているんです。だからその……伯父さんのところでも便利仕事に使われてるってわけです」そう言って笑いかけた。ようやく事態が飲み込めたので眺めてみると、背が高く真面目そうで、たぶん三十かもうちょいくらい、眼鏡をかけて血色はよくないけれど整った顔をしていた。高い鼻はわずかにくぼんで鼻筋が広い。口の形はシャープで、きれいな歯をしていた。髪は明るいブロンド混じりで、きれいになでつけられていた。なぜわかったのかはわからないけれど、すぐにわかった――この人はあまりお金も持たずになんとか暮らしていたことを。わたしと同様、伯父の世界とは無縁なことを。わたしにはほとんど興味を持ってないから恐れる必要はないことを。
乗車場でタクシーに乗り込むときに、彼が赤帽にチップをやった。
「払います」
「とんでもない」慌てて言うので、伯父のお金なのかと迷ったあげく、そうしてもらった。車は地下道にエンジンを轟かせていたけれど、唐突に街の真ん中に飛び出した。途端に喧噪と未知の世界がわたしを襲った。
「ニューヨークに来たことはあるんですか?」
「小さいころだったので覚えてはいないけれど。伯父さんは忙しいんですか?」
「来客をもてなしているので」
「あら。そういうのはリナおばさんが――」あまりに突然こちらを振り向かれたので口ごもる。「わたし……会ったことがないの。二人のどちらにも。言ってませんでしたっけ?」
「ライナさんは」キャロライナと韻を踏むように発音していた。おかしな声の調子。「外出していますから」
声をあげてしまった。おかしなことではないだろうか。なにしろ一面識もない姪が家にやってくるなんて、そうそうある出来事ではない。メソジストの教区牧師館ではこうはなるまい。
「悲しむことはありませんよ」
「悲しんでなんかいないわ」
「そうでしょうか」
「もちろん」
慌てたように説明してくれた。「まずいことを言ってしまった。六週間に一回くらいのペースで、伯父さんは友人たちと集まるんですよ。恒例の行事なんです。若かりし日々を懐かしむんでしょう」明るく爽やかな声だった。曖昧さや皮肉さえも薄らいでいるようだった。この人はわたしの知らないことを知っている。ことのときはまだ声に微妙に力の入っていることに気づけなかった。
「その集まりが、少なくとも伯父たちにとっては重要だとおっしゃるの?」
「ええまあ。伯父さんたち四人は旧友なんです。一緒に仕事をしていたとかどうとかと聞いています」こちらを振り向いた顔には、ためらいが見えた。「四人でゲームをしているんです」
「ゲーム? 何のゲームを?」
「パチーシ(インド双六)です」
「パチーシですって!」説明しようとしていたようだったけれど、彼がしゃべればしゃべるほどわたしは混乱した。
「ええ。なかなか熾烈なゲームです」と微笑んだ。「四人ともかなり熱くなってました」
「パチーシは知ってるわ。面白いけれど、でも伯父は……! まさか。賭けをしてるの?」
「お金ではありませんけどね。血を賭けてるんです」
明るく高めの声でそう言ったあとも、窓の外を眺め続けていた。
わたしは今の言葉の意味をなんとか理解しようともがいていた。「じゃあライナ伯母さんは四人きりにさせるために出かけてるんだ」
「かなり大きな家なんだけど」申し訳なさそうに顔を赤らめた。「よく出かけるんです」
「行き先は?」
「劇場、友だちとディナー……それに……コンサートとか、バレエを見に行ったり。……そんなところです」
「一人っきりで!」
「それは……違う」冷たい一言がわたしたちのあいだに漏れて置き去りにされた。
「伯父さんは家でパチーシをしているの?」
彼は笑い出した。少し優しげな声になった。「わかってるじゃないですか。四人は……そう、『産業界の海賊』と呼びましょうか」不安そうにこちらを見た。「『産業界の総帥』ってのは聞いたことがあるでしょう?」
わたしはうなずいた。
「四人は……好きこのんで騙し騙され合ってるわけです」
「戯れに?」
「まあそうです」それから急いで言葉を続けた。「ほかにやることもないのでぼくはウィンベリーさんとご一緒することも多いんですけど、ゲームには参加しません。だから列車が着くころだと伯父さんが口に出したとき……ぼくが迎えを買って出て……そうしてここにいるわけです」
タクシーが停車したのでわたしは外を見た。比較的閑静な通りで、自動車はすべて同じ方向を目ざしていた。目の前には高く冷たくびっしりと立ち並んだ家々があり、そのうちの一軒からは石造りの正面階段が大きな両開きの扉まで続いていた。視線をずらすと地下勝手口があり、鉄格子のついている窓が見えた。窓は閉まっており、ドア上の明かり取りから漏れる光のほかは何もない。二階には高さのある窓が三つあり、ブラインドがおりていた。
タクシーから降りると、コートの上から染み通るような冷たい風が襲ってきた。わたしはぶるぶると震えて家を見上げた。家の中がどうなっていようとも、メソジストの牧師館と似通ったところなどないのだろうということがよくわかった。
Charlotte Armstrong『Lay On, Mac Duff!』CHAPTER 1 の全訳です。
Ver.1 07/01/08
Ver.2 07/07/07
[訳者あとがき]
舞台となっているニューヨーク地図はこちら。
『Lay On,Mac Duff!』は、1942年に発表された、サスペンスの女王シャーロット・アームストロングのミステリデビュー作です。語り手のけなげな女の子が犯罪に巻き込まれて……という展開こそ後年のサスペンスものなのですが、探偵役はこの女の子ではありません。なんとシリーズ名探偵もの。本書に登場するマクダフことマクドゥガル・ダフは初期三部作で探偵役をつとめます。
サスペンスの女王が名探偵ものでデビューしていた!?となれば、謎解きものの才能がなかったからサスペンスものに転向したのかな、と下衆の勘ぐりもしたくなりますが、なかなかどうして愚直なまでに論理にこだわったパズラーでした。
本書の特徴は、何と言ってもとにかく大量の仮説の山。決定的な証拠がないために、マクダフはいくつもの可能性を徹底的にシミュレートします。真相が明らかになるまでは、可能性に可能性を重ねるしかなく、もはや推理というより砂上の楼閣、風前のトランプピラミッド。危うい机上の論理の綱渡りを最後まで渡りきってしまったアクロバティックな本格論理ミステリです。
可能性を一つ一つ潰していく過程で、一つの事実が二つの可能性を示唆しているのが明らかになったりするのが非常にうまい。どっちとも決めかねるまま、また新たな可能性が出てきたりして、けっこう複雑なんだけれど、一つの可能性が潰れた段階でもう一つの可能性も確定できたりと、けっこう考え抜かれた構成でした。意外なことに(?)伏線もいたるところにあるので要注意。
容疑者の人数が限りなく絞り込まれてさえ、あくまで論理にこだわる終盤には凄みすら感じました。これで最後に意外性さえあれば、クリスチアナ・ブランド級の大傑作になっていたかもしれません。が、読みどころが意外性にあるわけではないあたりに、むしろその後のアームストロングらしさを感じます。探偵ものの論理とはミスマッチな、語り手によるサスペンスも、往年のアームストロング節を堪能できました。
なお拙訳の底本には、1993年発行のZEBRA BOOKS版を使用しております。