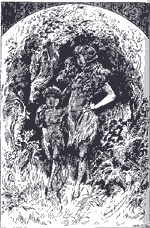 ※画像をクリックすると大きくなります
※画像をクリックすると大きくなります
あわい夢、神の怒れる手を逃れしもの――
静かに死せる母の胸の上に固くこわばった両の手は、
固くつよく握りしめても握り返すことはもはやない、
しとどに泣きじゃくる子どもをあやすことも――
もうすこしで、おとぎ話を
聞いてもらうのも、これでおしまい。君は愛しい
君にいたずらして生きる
ただいちずに愛し、戯れに怒るのは
妖精ブルーノ、陽気なやんちゃ者! 君を見た者なら誰だって、
知らんぷりなどできようか? ぼくはできなかった――
だいすきなシルヴィーに別れを告げなくてはならない、「さようなら!」[*註1.00]
肯定的か否定的かを問わず前巻に目を留めてくださった評論家の皆さんに、この場を借りて心からの謝意を表明させていただきます。否定的なご意見をいただくのはおおかた当然であったが、あまり肯定的なご意見を期待してはいなかった。どちらのご意見も本の宣伝に貢献してくれたことは間違いないし、世の読書人が意見をはぐくむ助けになったことは疑いない。ここで一言申し上げておくが、そうした批評のいずれを読むのも控えさせていただいたのは、なにも敬意を払っていないからではない。著者というものはいかなるものであれ自著の書評を読むべきではない。否定的な書評は不愉快にさせるし、肯定的な書評はうぬぼれを引き起こす。どちらも好ましくない結果を招くことになる。
だが個人的な消息筋から届いた批評のいくつかにはお答えしておこう。
そうした批評者の一人は、教会の説教と聖歌隊に対するアーサーの攻撃が厳しすぎると訴えている。お答えさせていただければ、本の登場人物が口にした意見には筆者は何一つ責任がない。それはただの意見に過ぎず、考慮に値するのであれば、おそらくは筆者から口に意見を放り込まれた人物たちが責任を負うことになるだろう。
別の批評者の方々からは、「あら〜ぬ」、「せ…ぬ」、「ひとりだび」という綴り上の改革[*註1.50]に異議を唱えられた。筆者としては、一般的な用法の方が間違っているという主張を申し立てることしかできない。「あら〜ぬ」について言うと、「ぬ」で終わるほかの言葉の場合にはすべて、「ぬ」が「ない」の短縮形だと言うことに議論の余地はないだろうが、「あらぬ」の場合にかぎって「ぬ」は「(あり)はしない」の代わりだと考えるのは馬鹿げていると言うほかない! 実際の話、「往ぬ」が「往った」という意味であるように、「あらぬ」は「あらった」という意味を表すべきである。また、「せ…ぬ」の点が必要なのは、「する」という単語がここで「せ…」に略されているからだ。だが点をつけずに「やらぬ」と綴るのが正しいのは、ここには「やる」という単語が完全な形で残っているからだ。「ひとりだび」のような言葉については、前の単語とくっつくときには後ろの単語の清音は濁り、でなければそのままというのが正しい原則だと考えている。この規則は多くの場合に守られている(例えば「選り+好み」は「よりごのみ」だが、「捧げる」は「さざげる」ではない)、そこでわたしは既存のルールをそのほかの場合に拡張しただけだ。しかし「似通う」はこの規則で綴られていないことは認める。だが語源的には「通う」だけで「似通う」の意味があったのだから、ここでは「似」は語幹と考えておくとしよう。
前作の序文にあった二つのクイズには、読者の方々も頭をひねってくださったのではないだろうか。筆者は五四ページ[*註1.75]頭から五七ページ後半にわたる一節に「埋め草」を三行つけ加えなくてはならないことに気づいた。一つ目は、その三行を見つけ出すことである。答えは五六ページの一一、一二行目。二つ目は、八篇からなる庭師の歌(七六、八八、九二、九九、一一〇、一一八、一五九、一六三ページ参照)のうち、(もしあればだが)どの歌が本文の文脈に合わせて書かれたのか、そして(もしあればだが)本文のどこが歌に合わせて書かれたかを判断するというものであった。最後の歌だけが本文に合わせて書かれたものだ。『木に潜り込んだ』何かの動物(確か鵜)の代わりに、『鍵で開いた庭の木戸』と書き換えた。八八、一一〇、一六三ページでは、歌に合わせて本文が書かれた。九九ページは歌も本文も書き換えることはなかった。相性がよかったのは幸運としか言いようがない。
前作の序文一三〜一五ページでは、『シルヴィーとブルーノ』の物語の成り立ちを説明しておいた。もう少し詳しい話をしても、読者の方々は我慢してくださることだろう。
短いおとぎばなし(一八六七年に「ブルーノの復讐」というタイトルで『ジュディおばさんの雑誌』のために書いたもの)が、もっと長い物語の核として使えるかもしれない、と思いついたのは、今思えば、一八七三年のことだった。筆者が思うに、第二巻の最終節の草案を思いついていたのだから、この物語は一八七三年に遡る。つまりこの節は刊行に付される機会を二十年も待ち続けていたのだ――文学作品の「
一八八五年二月には、本のイラストを描いてくれるようハリー・ファーニス氏と交渉をはじめた。正続二巻のほとんどはそのときには原稿の状態だった。筆者自身としては、全物語を同時に出版するつもりだった。一八八五年の九月、ファーニス氏から最初のイラストが届いた――「ピーターとポール」を描いた四枚だ。一八八六年の十一月には二組目が届いた――教授が歌う「ちっちゃな銃」を持つ「ちっちゃな男」を描いた三枚である。一八八七年の一月には三組目が届いた――「豚の尾話」を描いた四枚だ。[*註2.00]
私たちはこのようにして、順序のことは考えずに物語の一場面を描いたら次にはまた別の場面を描き続けた。一八八九年の三月になってようやく、この物語が何ページになるのか数えてみた。そこで物語を二つに分け、まずは半分を出版することにした。このため第一巻に結末らしきものを書かなければならなくなった。一八八九年十二月に第一巻が出版されたときには、ほとんどの読者がそれを本当の結末だと考えたのではないだろうか。いずれにしても、筆者が受け取った手紙のなかには、あれが最終的な結末ではないと疑っていたものはたった一通しかなかった。女の子からの手紙だった。「本を終わりまで読んだときにはうれしかったです。これでおしまいではないと気づいたからです。先生は続篇を書く予定があるとはっきり教えてくれてましたね」
読者のなかには、この物語を構成する原理を知りたがる方もいるかもしれない。もし本当に妖精がいて、ときどき私たちの前に現れたり、私たちが妖精の前に現れたりすることがあったとしたら。そして妖精がときには人の姿を装うことができるとしたら。あるいはまた――「密教」で体験するように、非物質的な霊的存在が現実的な移動をおこなって――人間もときどきは妖精の国にいることを感じるようになったとしたら。そういう場合に起こり得ることを明らかにしようとしたのだ。
人間というものは、以下のような意識の段階を経ることによって、さまざまな霊的状態になれるものだと筆者はつねづね考えていた。
(a)普通の状態。妖精の存在に気づかない。
(b)〈あやかし〉の状態。周囲の現実を知覚しながら、妖精の存在も知覚している。
(c)トランス状態。周囲の現実を知覚することなく、眠っているように見える状態。人(つまり人の霊的存在)は現実世界や妖精のほかの場所に移動している。妖精の存在を知覚している。
それにまた妖精というものは、妖精の国から現実世界に自由に行き来ができたり、好きなときに人間の姿になれたりするものだと考えていたし、またさまざまな霊的状態になれるものだと考えている。すなわち。
(a)普通の状態。人間の存在を知覚していない。
(b)一種の〈あやかし〉の状態。妖精が現実世界にいるであれば、人間の存在を知覚する。妖精の国にいるのであれば、人間の霊的存在の存在を知覚する。
ここで正続二巻のなかから、非日常状態が現れる箇所を表にしてみよう。
| 第一巻 | 語り手の場所 | 状態 | 他の登場人物 | 第二巻 | 語り手の場所 | 状態 | 他の登場人物 | |
| 027-039 | 汽車の中 | c | 長官(b)027 | 第一章 | 庭 | b | SとB(b) | |
| 050-068 | 同じく | c | 第三章 | 道 | b | 同じく(b) | ||
| 076-089 | 同じく | c | 四〜五章 | 同じく | b | 同じく、人の姿で | ||
| 092-105 | 宿 | c | 第六章 | 同じく | b | 同じく(b) | ||
| 110-119 | 浜辺 | c | 十〜十三 | 居間 | a | 同じく、人の姿で | ||
| 119-174 | 宿 | c | SとB(b)154-159 教授(b)163 |
第十四章 〜十五章 |
同じく | c | 同じく(b) | |
| 181-206 | 森の中 | b | ブルーノ(b)185-206 | 第十七章 | 喫煙室 | c | 同じく(b) | |
| 209-216 | 森の中、夢遊 | c | SとB(b) | 第十九章 | 森の中 | b | 同じく(a) ミュリエル嬢(b) | |
| 229-233 | 廃墟の中 | c | 同じく(b) | 廿〜廿一 | 宿 | c | ||
| 239,240 | 同じく、夢の中 | a | 廿二〜四 | 同じく | c | |||
| 240-245 | 同じく、夢遊 | c | SとBと教授が人の姿で | -end | 同じく | b | ||
| 246 | 通り | b | ||||||
| 253-267 | 駅など | b | SとB(b) | |||||
| 273-290 | 庭 | c | SとBと教授(b) | |||||
| 273-290 | 道など | a | SとBが人の姿で | |||||
| 307-315 | 通りなど | a | ||||||
| 318-335 | 森の中 | b | SとB(b) |
第一巻の序文(一三、一四ページ)で筆者は、本のなかで形になっている着想をどこから拾ったのか、いくつかお伝えしておいた。もう少し詳しくお知りになりたい方もいらっしゃるだろう。
第一巻一九〇ページ。鼠の死骸の一風変わった使われ方は、実体験に基づくものである。かつて筆者は、小さな男の子二人が庭で小型版「シングル・ウィケット」[*註3.00]をしているのを見かけたことがあった。バットはテーブル・スプーンほどの大きさだったと思う。その熱闘でボールが一番遠くまで届いた距離は、四、五ヤードかそこらであった。無論のこともっとも重要なのは、正確な距離である。距離はつねに慎重に計測され(打者と投手は友好的に協力し合っていた)。計測に使われていたのは鼠の死骸だった!
第一巻二三七、二三八ページでアーサーが引用した二つの似非数学公理(『同一のものより大きいものは、たがいに大きいものよりも大きい』と『すべての角度は等しい』)は、イーリから百マイルもない大学の学生が実際に、それも大真面目に発表したものである。
第二巻第一章、ブルーノのセリフ(『できるよ、その気になればね』など)は、実際に男の子が使っていた。[→該当箇所へ]
第二巻第一章のブルーノのセリフもそうだ(『なんて書いてないかはわかるよ』)。そして(『目をぐるんてしただけ』など)というセリフは、私のなぞなぞを解いた女の子の口から聞かされたものである。[→該当箇所へ]
第二巻第四章、ブルーノの独白(『お父さんがおウマさん』など)は、客車の窓から外を眺めていた女の子が実際に話していたことだ。[→該当箇所へ]
第二巻第九章、果物の皿を求める晩餐会の客のセリフ(『ずっと欲しいと思っていたものですから』など)は、偉大な桂冠詩人が用いていたのを聞いた。読書界全体がつい先ごろその死を悼んだに違いない。[→該当箇所へ]
第二巻第十一章、〈ミステル〉の年齢についてのブルーノの話は、この質問に対する女の子の答えを文字にしたものだ。『君のおばあちゃんは老婆心が強いかい?』『老婆かどうかわかんない』その子は慎重に言った。『八十三才よ』。[→該当箇所へ]
第二巻第十三章、〈妨害〉についての話は、私の想像の産物ではない! 『スタンダード』紙のコラムからそっくりそのまま写し取ったものだ。しゃべっていたのはウィリアム・ハーコート卿で、一八九〇年七月十六日当時、『国民自由クラブ』で〈野党〉の一員だった。[→該当箇所へ]
第二巻第二十一章、犬のしっぽに関する教授のセリフ『そっち側は咬まない』は、犬のしっぽを引っ張ると危ないと注意された子供が実際に使っていた。[→該当箇所へ]
第二巻第二十三章後半のシルヴィーとブルーノの会話は、ふと耳にした子供たち二人の会話を(「小銭」を「ケーキ」に代えただけで)そのまま記録した。[→該当箇所へ]
本書のなかのある物語――「ブルーノのピクニック」[*→第14章]――は、何度となく試しているので請け合えるが、子どもたちに話して聞かせるのにぴったりの物語だ。聞き手が村の学校にいる一ダースの女の子たちだろうと、ロンドンの応接間にいる三、四十人の客人だろうと、高校の百人だろうと、この物語を面白いと感じて、いつでも真面目に耳を傾け、ひたむきに鑑賞してくれるのがわかった。
この機会に、筆者自身もうまくいったと自負している命名に光を当てても構わないだろうか。第一巻五九ページ、〈シビメット〉という名は、副総督の性格を見事に表してはいないだろうか? ほったらかしにしているだけでまったく吹かないのであれば、真鍮のラッパほど無意味な家具もあるまいと、読者の方も確信されることだろう![*註4.00]
第一巻序文の一六ページで出しておいた二つのクイズを解こうと楽しまれた読者の方々は、次のクイズにも果敢に挑んでくれるのではないだろうか。次の対比のうち(もしあるのなら)どれが意図的であり、(もしあるのなら)どれが偶然かを見つけてほしい。
「小鳥」 出来事、と人
節 1、宴会
2、長官
3、皇后とほうれん草(第二巻第二十章)
4、総督の帰還
5、教授の講義(第二巻第二十一章)
6、もう一人の教授の歌(第一巻133ページ)
7、アグガギのかわいがられ方
8、ドッペルガイスト男爵
9、道化師と熊(第一巻123ページ)、子狐
10、ブルーノのディナーベル:子狐
このクイズの答えは、ただいま準備中の『オリジナル・ゲームとパズル』という小冊子の序文で発表するつもりだ。
最後に残しておいたが、真面目な話題が一、二個ある。
この序文では、前巻のとき以上にきっちりと「スポーツの道徳性」を論じるつもりであった。スポーツ愛好者からいただいた手紙を参考にするかぎりでは、人間にとっていかにスポーツが有益であるかがいくつも指摘され、動物が受ける苦痛など考えるだに値しないほど些細なことであると証明しようとしていた。
だがこの問題をじっくり考えて、賛否にわたる議論全体を整理してみた結果、この場で扱うにはあまりに大きすぎる問題だということに気づいた。いずれ、この問題について小論を発表したい。今のところは、筆者がたどり着いた最終結果を述べるに留めておく。
すなわち、神が人に与えたのは、食糧にするというような何らかの正当な理由があればほかの生き物の生命を奪ってもよいという、絶対的権利である。だが、その必然性がないのに苦痛を及ぼす権利を与えたりはしなかった。単なる娯楽や利益では、そうした必然性には入らない。したがって、スポーツ目的で苦痛を与えるのは、残酷であり、ゆえに不当なものである。だがことは筆者の予想より遙かに複雑であった。
筆者が「アーサー」の口から語らせた厳しい言葉に、反論の声が挙がった。二四九、二五〇ページ「説教」の話題と、二四八、二四九ページの合唱礼拝と「少年聖歌隊」についての箇所である。
物語の登場人物の意見を筆者が支持する可能性については、すでに反論しておいた。だがこの二つに関しては、筆者自身「アーサー」に賛成であることを認めよう。あまりにも多くの説教が我々の求めるところとは遙かに遠いところにあると思われる。したがって、多くの説教がなされるものの聞くに堪えない。それゆえに聞かないことが増えてしまう。今この文章を読んでいる方々も、日曜の朝には教会に行かれたのではないだろうか? ではもしよければ、聖句の原典を指摘したうえで、牧師がそれをどう練り上げたのか仰っていただきたい!
次に、「少年聖歌隊」とそれに関わるもの――楽曲、祭服、行進など――について言うと、「典礼」運動が痛切に必要だったことも、それがぎりぎりまで疲弊して干からびていた英国の礼拝に大きな進歩をもたらしたことも、認めるのはやぶさかではないが、価値ある運動のほとんどがそうなってしまうように、これも極端に振り切れ過ぎて新たな危険をいくつも生み出してしまったように思う。
信徒にとってこの新しい運動は、礼拝とは自分たちのために行われるものであり、提供すべきものは自分たちの肉体的存在だけだと思い始めてしまう危険をはらんでいる。信徒と同じく聖職者にとっても、こうした込み入った礼拝をそれだけで完結するものと見なしてしまい、礼拝が単なる手段であって我々の生活のなかに実を結ばないのであれば中身のない粉い物でしかないのだということを、忘れてしまう危険をはらんでいる。
少年聖歌隊にとっては、二四九ページ(註、「入湯」は「入場」の誤植である)で説明したように、虚栄心という危険や、自分たちの助けが必要とされていないのであれば礼拝のそうした部分には注意を払う価値がないと見なしてしまう危険、礼拝を単なる形式上のものと見なすようになる危険をはらんでいる――一連の行動を取り、言葉や歌を口にしているあいだも、心はここにあら〜ずで――「慣れる」ことで神聖なものへの「軽視」を助長する危険もはらんでいる。
最後の二つのタイプの危険について、筆者自身の経験から説明させていただこう。それほど前のことではないが、筆者は大聖堂の礼拝に出席し、聖歌隊のすぐ後ろの席に着いた。彼らにとって聖書の朗唱とは、さして重要視しなくてよいものであり、楽譜を揃えたり何なりするのにちょうどいい機会だと思われていることに、筆者は気づかざるを得なかった。少年聖歌隊が一並びに入場して位置に着き、祈ろうとでもするようにひざまずいて、いくらか時間をかけて周りに目をやってから立ち上がる光景もよく見かけたが、ただの見せかけに過ぎないのが見え見えもいいところだった。このように祈るふりをすることになれてしまうことが、子どもたちにとって危険であるのは間違いなかろうに? 神聖なものを不敬に扱う一例として、ある慣習に触れておこう。すなわち、聖職者と聖歌隊が行列する教会では、個人的祈りは聖具室に届けられ、会衆にはもちろん聞き取れないが、その終わりには、最後の「アーメン」が教会中に聞こえるほど大声で叫ばれることにほとんどの方はお気づきではないだろうか。これは、もうすぐ行列が現れるから立ち上がる準備をしなさいと会衆に合図するためである。そんな目的のためにこのように叫ぶことには議論の余地はない。「アーメン」と口にするのが本来は誰に対してなのかを思い出してほしい。それがこのように教会の鐘と同じ目的で用いられていることを考えると、あまりにも不敬なことであると認めざるを得まい? 聖書を足台として用いているのを目撃してしまったほどのことに匹敵する。
新しい運動によって聖職者自身にもたらされた危険の例として、筆者の経験による事実を述べさせてもらおう。国教会の聖職者たちには特にふざけた話を撒き散らす傾向が強く、極めて神聖な名前や言葉――ときには聖書の原文――が、冗談の種としてよく使われている。こうしたことがもともと子どもの口から飛び出していた通りに繰り返されているのだが、悪に対して完全に無垢な子どもなら神の目から見てあらゆる非難から免れもしよう。だが冒涜的な喜びのネタにするためにこうした無垢な発言を意識的に用いているような人々に対しては、話が別である。
しかしながら声を大にして言いたいのは、こうした冒涜はたいていは無意識のものである、と筆者が確信しているということだ。「環境」によって(第二巻第八章[*→該当箇所へ]で説明しようと試みておいたように)、人と人とのあいだにはあらゆる違いが生じる。こうした不敬な話の多くが――筆者にとっては聞くのも痛ましく、繰り返すことにも罪を感じるだろうが――聖職者たちの耳には何の痛みも与えず、良心に何の打撃も与えないというのは結構なことだ。あるいは聖職者たちが筆者と同じく心から「願わくは御名を崇めさせたまえ」および「汝らの心つれなきより、また汝らの言葉と誡命を侮りしより、神よ、我らを救い給え!」という二つの祈りを唱えられるのも結構なことだ。それに加えて、彼らと筆者自身のために、キーブルの祈りを付け加えさせていただきたく思う。「祈りにこたえてみそばにはべらせ、この日とすべての日々、我らを救いたまえ!」。実際問題として、そのこと自体よりもむしろその結果のために――説教者と会衆の双方にとって深刻な危険を伴っていることを考えると――社交的な場面でこうした冒涜的な話をする癖が聖職者にあることを残念に思う。信心深い会衆がこうした冗談に耳を傾け楽しんだりするだけで、神聖なものを崇拝する気持を失わせてしまうという危険をもたらしているのだ。さらには他人を楽しませるために自分が聞いたことを吹聴したいという誘惑もある。公に認められている伝道者がその信頼を裏切る光景を不信心な会衆が目にすれば、自分たちの考え方は正しかったのだというお墨つきを与えることになる。説教者自身にも、信用を失うという危険を必ずやもたらすことになる。確かにこうした冗談に関して、危険性を意識せ…ずに口にしているとしたら、同時に、我々の言葉に耳を傾けるリアルな神の存在も意識せ…ずに口にしているに違いない。普段からその意味も考えずに神聖な言葉を口にして恥じないのであれば、その人間にとって神は作り物になり天国は絵空事になってしまったことに気づくのは確実であるし――生命の灯が失せ、心の底では「手に感じるほどの暗闇[*註5.00]」に迷った無神論者であることに気づくのも確実である。
残念ながら現在では、神の名や宗教に関する話題を扱うにあたって、敬意をおろそかにする傾向が強まっている。劇場のなかには、舞台上で聖職者をひどく風刺して、憂慮すべきこうした傾向を助長しているところもある。聖職者のなかには自らこの傾向を助長している者もいる。崇拝心というものは法衣とともにうっちゃっておくことができ、教会の外に出れば、教会の中でこそ盲目的ともいえる敬意を払っていた名前や御物のことも、冗談のように扱うことができると知らしめているのである。「救世軍」がよかれと思ってやっていることも、残念ながら神聖なものを気さくに扱うせいで、このことを助長している。「御名を崇めさせたまえ」という心を持って過ごしたいと考えている人間であれば間違いなく、どんなにささいなことであれ、このことを止めるためにできることをすべきである。そういうわけだから、このような類の本の序文としては不適切な話題であるかもしれないが、長いあいだ心の中にわだかまっていた考えのいくつかを表明するために、こんなにも素晴らしい機会を与えられたことをうれしく思う。第一巻の序文を書いたときには、これほど多くの方々に読んでもらえるとは予想もしていなかった。だがありがたいことにたくさんの方に読んでもらったと信じるに足るしるしが届いているし、願わくばこの序文もそうなることを祈っている。なかには筆者がこの先に書き留めておいた見解に同意する用意のできている方もいらっしゃるだろうし、祈ったり手本となったりして社会から消えかけている精神を、崇拝の気持を復活させることに一肌脱ぐ用意のできている方もいらっしゃることだろう。
一八九三年、クリスマス
"Sylvie And Bruno Concluded" Lewis Carroll -- 'Preface' の全訳です。
本文中のページ数は、ちくま文庫版『シルヴィーとブルーノ』正編のページ数です。
Ver.1 03/03/13
Ver.2 03/05/20
Ver.4 10/10/15
[註釈]
▼*註1.00 [献詩] アクロスティック。各行の初めから三文字目を拾うと、イニッド・スティーブンズという、キャロルの友人の少女の名前になります。[↑]
▼*註1.50 [綴り上の改革] それぞれ原文では、「ca'n't」「wo'n't」「traveler」となります。
原文を直訳すると以下の通り。
「is't」が「is it」の短縮形であるように、「can't」は「can it」の短縮形。「wo'n't」は正しい。なぜなら「would」が「wo」に省略されているから。だが「don't」はこのままでよい。「do」が完全な形で存在してるから。その音節にアクセントがあれば、子音は二つ重なる。「preferred」には「r」が二つだが、「offered」には一つ。「parallel」はこの規則どおりではないが、語源を見れば「l」が二つなのも理解できる。[↑]
▼*註1.75 [54ページ] ちくま文庫の邦訳『シルヴィーとブルーノ』正編54ページ。以下、正編邦訳のページ数はちくま文庫版による。(ただし手許にあるのは1995年の第五刷。その後、改版・字組変更などで変わっている可能性もあり)。[↑]
▼*註2.00 [「ピーターとポール」ほか]
【ピーターとポール】



【豚の尾話】
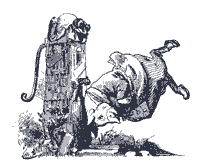
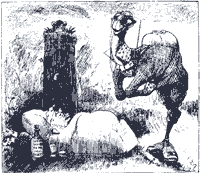
 [↑]
[↑]
▼*註3.00 [シングル・ウィケット] 「シングル・ウィケット」とは、ウィケット(柱)が一つのクリケットのこと。ベースはホームと一塁しかない。
〔1〕アウトにするには。
・フライを捕る。
・ベースの後ろに立ててあるウィケットを倒す。
〔2〕得点するには。
・ホームランを打つ。
・打ってから、向かいのベースに向って走る。ボールが届く前にたどり着けば得点。返球がもたついているようなら、そのあいだ何度でもベース間を往復して、得点を稼ぐことができる。
・ただしベースにたどり着く前にウィケットを倒されてしまうとアウト。[↑]
▼*註4.00 [シビメット] 原文「sibimet」。「sibimet」とは、ラテン語で「自分たちだけで自分たちに」の意。「sibilant」は「シューシューいう」。イマイチよくわからないが、無用のラッパのような役立たずである副総督は、誰からも吹いてもらうことなく、勝手に何でも自分だけでやってる(sibimet)ということか。[↑]
▼*註5.00 [手に感じるほどの暗闇] 出エジプト記、10:21。「主はモーセに言われた。『手を天に向かって差し伸べ、エジプトの地を闇に臨ませ、人がそれを手に感じるほどにしなさい。』」(新共同訳)。[↑]