暗澹たる空模様のある朝、若いハリイ・ゴスリングは死刑執行人に手足を縛られながら、自分の死体埋葬に関する指示に耳を傾けていた。薄暗い刑場の光を受けたハリイは頭巾をかぶせられ、絞首台への階段を引きたてられるように一歩一歩登って行った――絞首索が首に巻きつけられ、ぐっと床が落ち、あたりが闇に包まれる……。
だが、この死刑囚ゴスリングは、実は無実の罪を着せられて死んだのだ。首つり判事の異名をとる峻厳な判事ブリテンのために!
その数年後、ノーフォーク州最北端の寒村モクストンにティールと名乗る浮浪者風の男が現れた。村の一番奥のコテージに住むジョン・ウィロビーを訪ねてきたのだった。ウィロビーは、一年半ほど前から、時々村に来ては何日か泊っていくようになった男で、まともな紳士然とした人物だが、彼が何者なのか、どこに住んでいるのかは、誰も知らなかった。一方ティールは、村に来て二日目の夕方、ウィロビーの家へ行くと言って宿を出たが、それきり行方不明になってしまった。やがてウィロビーも村を去り、何の手掛りもないまま三週間が過ぎた頃、ウィロビーの家の回りに異臭が漂いはじめ、庭の古井戸からティールの死体が発見された。警察はさっそく、ウィロビーの身元を調べ始めたが……。
無実の死刑囚の死とノーフォークの寂しい寒村に起きた奇怪な事件のあいだに、一体どんなつながりが?
イギリス文壇に特異の存在を示すハミルトンの、現代法制と社会の歪みを鋭く突いた、異色の傑作。
これが裏表紙の粗筋。一読して見当がつくとおり、本書の内容は『歯と爪』であり『黒衣の花嫁』であります。このサスペンスの名作二篇に劣らぬ面白さでありました。章によって視点人物が変わるのが実に効果的。まずは死刑囚。次に謎の男ティール。ティールが泊る宿屋の主人。ティールの失踪を捜査する警官。ティール事件の陪審員の一人。宿屋の亭主は、いかにも小さな村の宿屋の亭主らしく、村のことなら任せてくれ的な人間観察。警官は警官らしい観察眼と正義感に基づく、警察小説のような視点で。陪審員は世間の代表として好奇心いっぱいに裁判の成り行きを見守ります。この陪審員が面白い。人間心理に一家言持つ時計屋デニス。彼のおかげで、法廷ミステリの緊迫感とはまた別の野次馬的裁判シーンが誕生しました。人がテレビを見ながらツッコミを入れている感覚に近いと言えばいいかな。国会を戯画化したような場面もあり、割とユーモラスな雰囲気も漂っていたりするのでした。
かくして謎めいた発端、警察の捜査、気になる裁判の行方……そして明かされた真相は、というところで残念ながら納得できません。重要な登場人物二人が偶然出会ったというのがあまりにご都合主義。それだけならまだ、偶然出会ったからこそ事件が起きたのだ、という好意的な見方もできる。けれど、財布が防水だから事件の鍵を握る重要な手紙が水に浸かってもきっと大丈夫、という超楽観主義には呆然。どんな財布だよ。
復讐される側の悪者っぷりがイマイチ伝わってこなかったのも残念。無実の罪のハリイ死刑囚にしても、本人の言葉を信じるならば無罪なんだろうけど、はっきりしない。とはいえ犯人の目的(というか作者の目的?)の第一が、復讐ではなく冤罪に対する警鐘だとすればそれも意図的なものか。悪人の悪人たるゆえんをじっくり描けば、勧善懲悪の物語になってしまう。復讐される側の罪も復讐する側の罪も曖昧なまま。神ではない人間には真相を透視することなどできないのだから、たとえ自白があろうと証拠があろうと、自白が嘘かもしれないし証拠が捏造かもしれない可能性は常にあるのだ。ということだろか。
だけど作者の意図がそうであるにしろ、読み終えてすっきりしない以上は、その意図が成功してるとは思えない。
復讐される者が最後に言う台詞「きつとこの手でやつたに違いない/しかし、思い出せん。それに、自分でやつたとは思わない/自分でやつたとは思わないんだ!」は、『歯と爪』における「Who done it?」の連呼に匹敵する名台詞。 |
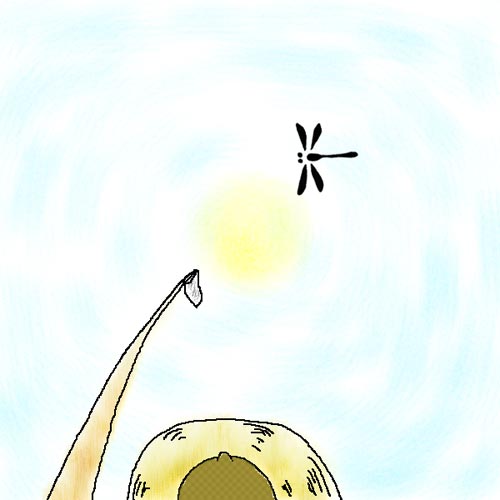
 『現代短歌の鑑賞101』より
『現代短歌の鑑賞101』より