
それから一、二か月のあいだは、反動で一人きりの都会生活がいつもとは違って退屈で飽き飽きしたものに感じられた。エルヴェストンに残してきた素晴らしい友人たちが恋しくなった――気の置けない意見のやりとり――人の思考に新鮮な現実をもたらす共感。だが、おそらく何よりも恋しいのは、仲良くなった二人の妖精――あるいは夢の子供たち――のことだ。ぼくはまだ、あの甘美な明るさでぼくの人生を魔法の輝きで照らした二人が何者/何物だったのかという問題を解き明かしてはいないのだ。
仕事をしているあいだ――案ずるに多くの人をコーヒー挽きやしわ伸ばし器[*1.00]のような精神状態にさせる時間――には、いつものように時間は飛び去ってゆく。一休みしているあいだは、本や新聞も満たした腹には睡眠薬代わりでしかなく、わびしい思いに引き戻されるような、孤独な時間である。ここにいない親友の顔で虚空を満たそうとするが――まったく無駄に終わり――そのこと自体に孤独の本当のつらさを気づかされる。
ある晩、いつも以上に退屈な気分を抱えてクラブに立ち寄ったときも、そこで友人に会えるなんて期待はさほどしていなかった。今やロンドンは「町外れ」なのだから、せいぜいいここで「人間らしいおしゃべりの心地よい言葉」を聞き、人間らしい考えと触れ合いに行くのだという気持があったくらいだ。[*2.00]
ところがそこで最初に見つけたのは友人の顔だった。エリック・リンドンがずいぶんと「退屈した」顔つきで新聞の上をだらだらとさまよっていた。そこでぼくらはお互いにうれしさを隠そうともせ…ずにすっかり話に夢中になっていた。[*3.00]
しばらくしてから、ちょうどそのとき頭のなかを占めていた話題に触れてみることにした。「ところで先生は」(この呼び名を使うのがぼくらの暗黙の同意事項だった。堅苦しい「フォレスター医師」と、親しげな――エリック・リンドンがそう呼んだことはほとんどなさそうだが――「アーサー」を折衷した妥協案である)「今ごろは外国だと思いますが、よければ住所を教えてもらえませんか?」
「まだエルヴェストンにいますよ――たぶんね」それが答えだった。「ですがこのあいだあなたと会ってからこっち、あそこには行っていないので」
この報せのなかで一番驚いたのはどの部分だっただろう。「でも――失礼ですが――結婚式はいつ――ことによるともう挙げてしまったんですか?」
「いいえ」エリックの声はこわばっていて、ほとんど何の感情も込められてはいなかった。「あの婚約はなくなりました。ぼくは未だに〈未婚のベネディック〉です」[*4.00]
そのあとはいろいろな思いが――アーサーの幸せにとって新たな希望の光で満ちた思いが――到来して、うろたえたあまりにそれ以上は話も続けられず、喜びのあまり折りを見て丁寧な断りを入れるのも忘れて黙り込んでしまった。
次の日、ぼくはアーサーに手紙を書いて、長いあんだ音沙汰がないのはひどいじゃないかと、あら〜んかぎりの言葉で責め立て、いったい何があったのか教えてくれるよう頼んだ。
返事が来るまでは三、四日――あるいはもっと――かかるだろう。一日一日というものがいっそう退屈なうえにだらだら長々と進むものだとはちっとも知らなかった。
時間をつぶすつもりで、ある日の午後、ぼくはケンジントン公園までぶらついて、目の前の小径をどれということなく当てもなく歩いていると、いつの間にか、なぜかまったく知らない小径に迷い込んでしまった。それでも、不思議な経験のことはぼくの生活から完全に薄れてしまっていたようだ。ふたたび妖精の友達に会いたいということしか考えていなかったというのに。そのとき、ほんの偶然から、小さな生き物が小径を縁取る芝生のなかを動いていることに気づいた。昆虫でも蛙でもないようだし、といってほかにどんな生き物かと言われても見当がつかない。ぼくはそっと膝をついて両手で囲い込み、動き回る小動物を捕らえた。そこで突然、驚きと喜びをぞくぞくと感じたのは、その囚われ人がほかでもないブルーノだったと気づいたからだ!
ブルーノは極めて冷静に事態を受け止めていたので、会話しやすいような距離を取って地面に降ろしてやると、このあいだ会ったのがつい数分前でしかないかのように、しゃべり出した。
「決まりをしらないの?」ブルーノが問い詰めた。「どこにいたのか言わなかっているうちに、妖精をつかまえるときの?」(ブルーノの文法は、このあいだ会ったときから全然上達していなかった)
「うん。妖精のことで決まりがあるなんて知らなかったよ」
「あーたにはぼくをたべる権利があると思うな」小さき友人は勝ち誇ったような笑みを浮かべてぼくを見上げている。「でもあんまし自信はない。訊かずるにたべないほうがいいよ」
しかるべき質問もせ…ぬうちは、そんな取り返しのつかない行動を取らないというのは、なるほど道理にかなっている。「真っ先に訊くことにするよ。それに、君に食べるだけの値打ちがあるかどうかもまだわからないしなあ!」
「おいしいくらいに食べごろだと思うけどな」ブルーノの満足げな声を聞いていると、それが誇らしいことでもあるかのようだった。
「それで、ここで何をしてるんだい、ブルーノ?」
「ぼくはそんな名前じゃないよ!」いたずらっ子はそう言った。「ぼくの名前は『まあブルーノ』じゃなかった? シルヴィーはいつもそう呼んでるよ、ならったことを口にするとさ」
「よしわかった、ここで何をしてるんだい、まあブルーノ?」
「勉強してるんだ、もっちろん!」いたずらっぽく目を光らせるのは、ナンセンスなことを話していると自覚しているときの癖だった。
「それが君の勉強の仕方かい? ちゃんと覚えたかな?」
「ぼくの勉強ならいつだっておぼえれるよ。むじかしすぎておぼえれないのはシルヴィーの勉強さ!」頭が痛いよ、といったふうに顔をしかめると、額をとんとんと叩いた。「ちゃんとにわかるとは思えないよ!」どうしようもないらしい。「きっと二倍ぶん考えなきゃだめなんだ」
「ところでシルヴィーはどこに行ったの?」
「ぼくも知りたいよ!」ブルーノはうんざりとして口をとがらせた。「ぼくに勉強の用意をさせてなんの役にたつんだろう、シルヴィーがここにいてむずかしいのを噛んで含んでくれなきゃさ」
「君のためだ、シルヴィーを探そう!」とぼくは買って出た。立ち上がって、もたれていた木陰の周囲をうろうろし、くまなくシルヴィーを探して歩いた。しばらくすると、またもや見慣れぬものが芝生のなかを動き回っていることに気づいたので、膝をつくと、すぐ目の前にシルヴィーのあどけない顔があった。ぼくを見ると驚いて顔をぱっと輝かせ、あのかわいらしい声で話しかけてくれたのだが、ぼくは初めの方を聞き逃してしまい、聞こえていたのは話の終わりのようだった。
「なのでもう終わってると思うので、戻ってみます。ご一緒なさいますか? この木の反対側の辺りなんです」
それはぼくにはほんの数歩だったが、シルヴィーには何十歩という距離だった。置いてきぼりにして見失ってしまわないように、できるだけゆっくりと歩かなくてはならなかった。
ブルーノのお稽古を見つけるのは簡単すぎるくらいだった。どうやらつやつやした大きな
〈まずは喜び、務めは後で〉が、この小人族たちのモットーであるらしく、何より先に何度も抱き合ってキスを交わした。
「さあ、ブルーノ」シルヴィーはおかんむりだ。「『それまで』って聞こえるまでは、勉強を続けるはずじゃなかった?」
「でもそれどころか聞こえたんだ!」ブルーノはいたずらっぽく目を輝かせた。
「何が聞こえたの、こら?」
「空耳がね。蔦わってきたんだ。聞いてない、あなたさん?」
「どっちにしたって、あんなところで眠らなくたっていいでしょう、ねぼすけなんだから!」ブルーノは特大の〈お稽古〉の上で丸くなり、もう一枚を工夫して枕にしていたのだ。
「寝てなかったよ!」ブルーノはざっくり傷つけられたような声を出した。「目を閉じてるのは、起きてるって合図なんだから」
「わかったわ、それで、どれくらい覚えたの?」
「ちょっとすごく少しだけ」勉強の成果を大きく見せるのを明らかに嫌がって、ブルーノは控えめに答えた。「それ以上は覚えらんないよ!」
「まあブルーノ! その気になればできるはずよ」
「もちろんできるよ、その気になればね」青ざめた学徒は答えた。「でもその気になれないんだ!」
シルヴィーには――それほど感心はできるやり方ではないが――ブルーノの難解な屁理屈をはぐらかす方法があった。不意をついて別の話題を始めるのだ。今もこの見事な作戦を実行した。
「ねえ、ひとつ言っておくけど――」
「しってる、あなたさん?」ブルーノがさも重要そうな顔をした。「シルヴィーは数が数えれないんだ。いっつも『ひとつ言っておくけど』って言うんだけど、ぜったいふたつ言うんだ! いっつもそう」
「ふたつの頭脳はひとつに勝るって言うよ、ブルーノ」とは言ったものの、ぼくは自分でも何を言いたいのかよくわからなかった。
「頭がふたつあっても気にするもんか」ブルーノはそっと自分に言い聞かせた。「ひとつはご飯をたべる頭、ひとつはシルヴィーとけんかしる頭――頭がふたつあったら、もっとかわいくに見えると思う? あなたさん?」
疑う余地なし、とぼくは請け合った。
「だからシルヴィーはおこりんぼなんだ――」ブルーノは真剣だった。悲しそうでさえある。
シルヴィーはこの思わぬ方向からのアプローチに驚いて目を見開き――バラ色の顔が喜びに輝いた。だがシルヴィーは何も言わなかった。
「勉強が終わってからぼくと話す方がいいんじゃないかな?」
「いいよ」ブルーノがあきらめき顔で答えた。「そんときシルヴィーがおこりんぼしなければね」
「お勉強は三つしかないじゃない」シルヴィーが言った。「書取、地理、音楽」
「算数はないんだ?」ぼくは尋ねた。
「ええ、ブルーノは算数向きの頭をしていないんです」
「そりゃそうさ!」とブルーノ。「ぼくのの頭は髪の毛専用だもの。いろんな頭をしてるわけないじゃん!」
「――九九の算術が覚えられないし」
「歴史ならだいすきなんだけどな」ブルーノが答えた。「ご九ろう算の術はシルヴィーがくり返すてよ――」[*5.00]
「ええ、だからあなたも繰り返して――」
「だけどさ!」ブルーノがさえぎった。「シルヴィーやぼくがくり返さなくても、歴史はくり返すんだから。教授が言ってたもんね!」
シルヴィーが板に文字を書いた――「て・き・い」。「さあ、ブルーノ。なんて書いてある?」
ブルーノはしばらくのあいだ真面目に黙って眺めていた。「なんて書いてないかはわかるよ!」ついに音を上げた。
「だめよ」シルヴィーは言う。「なんて書いてある?」
ブルーノはその不可解な文字列を改めて眺めた。「ああ、反対向きの『いきて』だ!」と叫んだ。(確かにその通りだと思う)
「どうやったらそんなふうに見えちゃうの?」シルヴィーがたずねた。
「目をぐるんてしただけ。それからまっすぐ見るの。カワセミの歌をうたっていい?」
「次は地理よ」シルヴィーは言った。「それが決まりでしょう?」
「そんなにたくさん決まりがないほうがいいよ、シルヴィー! 考えったんだけど――」
「そうね、決まりはたくさんある方がいいわよ、おばかさん! だいたいどうやって考えるつもり? 今すぐその口を閉じなさい!」
ところが『その口』が自分から閉じる気配はなさそうだったので、シルヴィーが閉じてやった――両手で閉じて――それから手紙に封をするように、キスで封をした。
「ブルーノのおしゃべりに鍵をかけたので」と言ってシルヴィーがぼくを見た。「勉強するときに使う地図をお見せします」
地面に広げられたのは大きな世界地図だった。あまりに大きいのでブルーノは「
「飛んでるてんとう虫子さん、カワセミ王に声かけられた。『じんセイロンいろあるけれど、きみは素敵でいいカンディア!』捕まえてからこう言った。『メディアくじゃなければこれからどう? お茶がいいかな、ごハンガリーかな。ヌビアガーデンで一杯どう?』爪でつかんでこう言った。『欧州そう』口でつまんでこう言った。『なかなかインド』ごくんと飲み込みこう言った。『お味がイートン』おしまい」
「まったく問題ないわ」シルヴィーが言った。「じゃあ
「コーラスしてくれる?」ブルーノがぼくに言った。
「残念だけど歌詞を知らないから」と言いかけたときだった。シルヴィーが何も言わずに地図をめくると、裏には歌詞が書かれていた。ある点で非常に変わった歌だった。コーラスがひとまとまりの歌詞の最後にではなく、真ん中に組み込まれてる。だが曲はわかりやすかったのですぐに覚えて、うまくコーラスすることができた。まあ、そんなことをひとりきりでうまくやれる分には、だけれど。手を貸してくれるようシルヴィーに合図したけれど駄目だった。シルヴィーはかわいらしく笑って首を振っただけだった。
 【*註6.00】
【*註6.00】
カワセミの王様が天道虫にプロポーズ――
〈歌え おまめ 歌え おめめ 歌え おみくじあめ!〉
「もっか敵なし
「頭も素敵だし――
「白い髭ならまるでチーズ――
「おしゃべり好きのぼくのお目々!」
天道虫は言いました「頭と言えばやっぱりまち針」――
〈歌え プラム 歌え プリマ 歌え プラハの熱帯夜!〉
「どこでも刺したら
「ピタッと止まる。そんな針なら
「わたしにぴったり
「そわそわ頭なんか嫌!」
天道虫は言いました「髭があるなら牡蠣だって」――
〈歌え はえ 歌え はね 歌え ハレー彗星観測隊!〉
「牡蠣は大好き。なぜなら
「お口を閉じてるから
「王冠かぶせてあげたって――
「なんにも言わない、もう絶対!」
天道虫は言いました「針にも目がある、あしからず」――
〈歌え 猫 歌え 鋸 歌え ニコチン中毒!〉
「針のおめめはとっても鋭い――
「陛下の目とは大違い
「もう行って。――プロポーズ?
「お気の毒!」
「で、王さまは行っちゃったんだ」歌が終わると、ブルーノがその後を教えてくれた。「いつもとなんも変わらずに」
「まあ、ブルーノ!」両手で耳をふさぎながらシルヴィーが叫んだ。「『なん』も、じゃなくて、『なに』も、でしょ」
ブルーノは言い返した。「『なに?』って言うのは、シルヴィーの声がちっちゃくて聞こえないときだけさ」
「王様はどこに行ったんだい?」喧嘩になるのを防ごうとしてぼくはたずねた。
「もっと彼方だよ」ブルーノが言った。
「『もっと彼方』じゃないわ」シルヴィーが訂正した。「『はるか彼方』よ」
「そんならさ、おやつのときも、『「もっとナッツ」をちょうだい』、じゃないよね」ブルーノが言い返した。「『「
今回はシルヴィーは知らんぷりして相手にせ…ず、地図を巻き始め、「授業は終わりよ!」とかわいらしい声で宣言した。
「音をあげたところはなかったかい?」ぼくはたずねた。「男の子はみんな、授業のあとで泣き言をこぼすものだろう?」
「十二時過ぎたら泣くないの」とブルーノが答えた。「晩ごはんが近いから」
「ときどき朝に」シルヴィーがささやいた。「地理のときや、反抗的なとき――」
「なにしゃべってんのさ、シルヴィー!」ブルーノが急いでさえぎった。「世界はシルヴィーのおしゃべりのためにあるんじゃないでそ?」
「へえ、それならどこでしゃべればいいの?」明らかに議論を始めそうな勢いだ。
だがブルーノの答えはきっぱりとしていた。「言い合いはやだ。遅くなるし、時間もなくなっちゃうし――なのにシルヴィーはすごく好きなだけいつまでもさ!」そう言って手の甲で目をぬぐった。そこには涙が光り始めていた。
シルヴィーの目にもすぐに涙があふれた。「そんなつもりじゃなかったの、ブルーノ!」そうささやくと、〈ネアイラの髪のもつれの中に〉議論は埋もれてしまい、二人は抱きしめ合ってキスを交わした。[*7.00]
だがこの新型の議論は、稲妻の閃光によって突然の終わりを告げられた。直後に雷鳴がとどろき、雨粒が滝のように落ちてきた。ぼくらが雨宿りしている木の葉の向こうで、生き物のようにコンコンパラパラ音を立て、ゴロゴロと唸っている。「狐の嫁入りってやつだな!」ぼくは言った。
「お嫁さんは先に落ちちゃったんだね」とブルーノが言った。「いま落ちてるのはキツネさんだけだ!」[*8.00]
しばらくすると、始まったときと同じくぱたりと雨音が止んだ。木陰から出てみると、嵐は去っていた。だが戻ってみると小さな友人たちが見あたらない。嵐とともに消えてしまわれては、家に帰るほかなかった。
テーブルの上でぼくの帰りを待っていたのは、見ればすぐに電報だとわかるあの黄色い封筒だった。大多数の人間にとっては、突然降りかかった大きな悲しみ――生命の輝きに、この世から完全に飛ばされることはできないあの影を落とすもの――と分かちがたく結びついているに違いない[*9.00]。もちろん――多くの人間が――突然の吉報を受け取ったこともあるに違いない。だがそんなことはおそらくめったにないだろう。人生というものは総じて、喜びよりも悲しみの方が多いのではないだろうか。それでも世界は回る。理由など誰にもわかるまい?
だが今回はつらい衝撃に直面することはなかった。それどころかわずか数語だけ(「書ク気ニナレナイ スク ニ来イ イツテ モ歓迎 オツテ手紙ヲ アーサー」)と、まるでアーサー本人がしゃべっているようだった。ぞくぞくするような喜びを感じたぼくは、すぐに旅の準備に取りかかった。
"Sylvie And Bruno Concluded" Lewis Caroll -- Chapter I 'Bruno's Lessons' の全訳です。
Ver.1 03/03/24
Ver.2 03/05/17
Ver.3 03/05/20
Ver.4 03/09/12
Ver.5 03/12/22
Ver.6 04/10/07
Ver.7 04/10/16
Ver.8 04/12/13
Ver.9 05/01/06
Ver.10 10/10/15
[註釈]
▼*註1.00 [しわ伸ばし器]。 邦訳正編214ページにも、しわ伸ばし器のことが書かれています。ブルーノとシルヴィーが、教授が短くした鰐を元の長さに戻そうと、しわ伸ばし器のような機械で伸ばしたところ……。
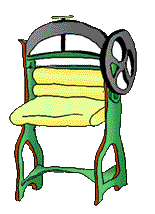 しわ伸ばし器。[↑]
しわ伸ばし器。[↑]
▼*註2.00 [人間らしいおしゃべりの]。原文では "sweet words of human speech"。かっこでくくられているので引用のようだが、不明。[↑]
▼*註3.00 [エリック・リンドン]。『シルヴィーとブルーノ』マーティン・ガードナーの序文によれば――この作品の登場人物はみな植物に関係した名前を持っている。
‘Lindon’は‘linden’(=シナの木)から。以下、アーサーの名字‘Forester’は‘forest’(=森)から。ミュリエル嬢の名字‘Orme’はラテン語で‘elm’(=楡の木)。 [↑]
▼*註4.00 [未婚のベネディック]。シェイクスピア『から騒ぎ』の登場人物。そこから、英語で「benedick」といえば「長い独身生活の果てに結婚した男」を指す。[↑]
▼*註5.00 [ご九ろう算の術]。ブルーノは「Multiplication-table(かけ算表)」ならぬ「Muddlecome-table(ごちゃごちゃ表)」と言っています。「muddle(混乱)」が「come(訪れる)」とは実に的確な命名です。[↑]
▼*註6.00 [カワセミとてんとう虫・挿絵]。ハリー・ファーニスによるイラストには、カワセミ王が立っている窓辺にマンドリンらしき楽器が描かれています。
・フロベール『紋切り型辞典』より。「マンドリン:スペイン女を口説くときの必需品。」
・チェーホフ『桜の園』より。「恋をしている男にとっちゃ、ギターだってマンドリンさね」
どうやらマンドリンは情熱的な恋を象徴する楽器のようです。[↑]
▼*註7.00 [ネアイラの髪の]。 ミルトン「リシダス」より。「リシダスが死んだというのにミューズに思いを馳せることに何の意味があろう、ニンフのアマリリスやネアイラの髪と戯れる方がましではないか?」という文脈。※リシダス翻訳全文はこちら。[↑]
▼*註8.00 [キツネさんだけ]。生き物のように「hissing and spitting」雨が降っている、と書かれています。「hiss」「spit」はいずれも猫の唸り声を表す動詞。英語で土砂降りのことは「it rains cats and dogs」と言いますが、聞こえるのが「hiss(シャーッ)」と「spit(ゴロゴロ)」だけで「bowwow(ワンワン)」が聞こえないので「dogs」はもうとっくに落ちちゃった後なんだね、というオチ。※訳語の「狐の嫁入り」は土砂降りではなく天気雨のこと指す語ですが大目に見てください。[↑]
▼*註9.00 [電報/大きな悲しみ]。正編序文には、序文を書いている途中に友人の死を報せる電報が届いたことが記されています。[↑]
[更新履歴]
・04/10/07 「かけ算の段も覚えないし――」/「好きなのは歴史なんだ」ブルーノが答えた。「合戦の段をくり返すてよ」
→「かけ算なんて、いつまでたっても六の段が覚えられないし――」/「歴史だいすき」ブルーノが答えた。「どくろだんをくり返すてちょだい」
・04/10/16 「だめだめ!」ブルーノがさえぎった。「歴史は自らくり返す。〜」
→「だけどさぁ!」ブルーノがさえぎった。「シルヴィーやぼくがくり返さなくても、歴史はくり返すんだから。〜」
・05/01/06 「歴史だいすき」ブルーノが答えた。「どくろだんをくり返すてちょだい」
→「歴史ならだいすきなんだけどな」ブルーノが答えた。「ボク降参じゅつはシルヴィーがくり返すてよ――」
・10/10/15 ▼「カワセミの王様」の語呂合わせを一部変更。「幸せいろんな」→「じんセイロンいろ」など。▼「more far」「farther」「more broth」「brother」のことば遊びを変更。「ほしいもっと/ほしイモ」→「もっとナッツ/ハルかナツ」。