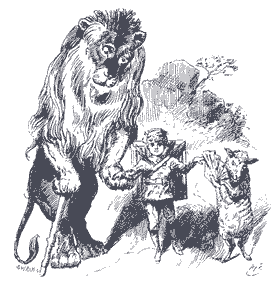
「禿げとるごとく禿げとります」困ったような答えが返ってきた。「さてブルーノ、お話があるんじゃが」
「ぼくもおはなしがあるよ」シルヴィーに先を越されるまいとして、ブルーノが急いで話し始めた。「むかしむかしネズミがおりました――とってもちっちゃなネズミです――うんとちびっちゃいネズミでした! 見たことがないくらいうんとちっちゃなネズミ――」
「そのネズミにはどんなことが起こったんだい、ブルーノ?」ぼくはたずねた。「ほかに話すことがあるだろう、ちっちゃいこと以外にもさ?」
「なんにもおこらなかったの」ブルーノが真面目くさって答えた。
「どうしてよ?」シルヴィーは座っていた。ブルーノの肩に頭をのせ、自分のお話をする機会を辛抱強くうかがっていた。
「すんごくちっちゃかったんだ」ブルーノが説明する。
「そんなの理由にならないよ!」ぼくは言った。「どんなに小さくたって、何か起こるんじゃないかな」
ブルーノは哀れむようにぼくを見た。まるでぼくのことを馬鹿だと思ってるような目つきで、繰り返した。「すんごくちっちゃかったんだよ。なにかおこったら死んじゃうよ――とてもすごくちっちゃかったんだから!」
「ちっちゃいことは充分わかったわ!」シルヴィーが口を挟んだ。「それ以上は考えてないんじゃない?」
「まだだよ」
「ほらね、じゃあ続きを思いつくまでお話をするのは待ってなさい! いい子なんだからお口を閉じて、私のお話を聞いてちょうだい」
あまりに慌ててお話を始めたせいで、ブルーノの思いつきをすっかり枯れてしまったらしく、おとなしく聞き役に回って、「もうひとりのブルーノのおはなしして」とねだった。
シルヴィーはブルーノの首を抱きしめて、話し始めた――。
「風が木々の隙間にささやく――」(「ぎょうぎが悪いね!」とブルーノが口を挟んだ。「お行儀のことは気にしないで」シルヴィーは言った。)「夜のこと――月のきれいな夜のことでした。梟がホーホーと――」
「フクロウじゃないってことにしてよ!」ブルーノはむちむちした手でシルヴィーの頬を撫でた。「フクロウは好きじゃないんだ。あんなおっきな目してさ。ニワトリってことにしてよ!」
「あの大きな目玉が怖いのかい、ブルーノ?」ぼくは言った。
「なんもこわくないけどさ」ブルーノはできるだけ無頓着を装って答えた。「おっきな目でみっともないでそ。泣いたりしたら、なみだもおっきいよ――もう、月みたいにおっきいんだ!」そう言って楽しそうに笑いだした。「フクロウはいったい泣くのかなあ、あなたさん?」
「梟はぜったい泣かないよ」ぼくはブルーノの話し方を真似ようと、かしこまって答えた。「悲しいことなんてないからね」
「ええっ、そんなことあるよ!」ブルーノが叫んだ。「いっつもとても申しわけないとおもって悲しんでるよ。だってかわいそうなちびっちゃいネズミを殺すんだから!」
「でもお腹がすいているときなら、悲しくて申し訳ないとは思わないんじゃないかい?」
「フクロウのことなんにも知らないんだ!」ブルーノが見損なったような口の利き方をした。「おなかがすいてるときには、すごくすっごく悲しくて残念だとおもいながらころすんだから。だってころさなかったなら、晩ごはんになってたんだから!」
危険極まるブルーノの空想癖が頭をもたげてきたのを見てとって、シルヴィーが割って入った。「さあお話を続けるわよ。それで梟は――鶏は、ね――晩ごはんには太った見事な鼠を見つけられたらいいなと――」
「みごとなンサギにしてよ!」ブルーノが言った。
「でも鼠を殺すのは見事な詐欺じゃないもの」シルヴィーが言い返した。「そんなのダメよ」
「『サギ』なんて言ってないよ、ぶー!」ブルーノの目にはいらずらっぽい輝きがきらめいていた。「『ンサギ』だよ――野はらを走るやつ!」
「ウサギ? わかったわ、だったら兎にします。だけどこれ以上わたしのお話を変えたりしないでちょうだい、ブルーノ。鶏が兎を食べるわけないじゃないの!」
「でもさ、ためしに食べてみたくてンサギを見つけようとしてたかもしれないもの」
「そうねえ、ためしにだったら――まあブルーノ、そんなわけないでしょ! 梟に戻しますからね」
「うん、それじゃあ、目はおっきくないってことにして!」
「やがてかわいい男の子が現われました」これ以上変えられては叶わないと、シルヴィーは話を続けた。「男の子はお話を聞かせてちょうだいと頼みました。すると梟はホーホー鳴いて飛んで行ってしまいました――」(「『飛んでく』じゃなくて、『飛ぶでく』でしょ」とブルーノがささやいたが、シルヴィーは無視した。)「次に男の子はライオンに出会いました。お話を聞かせてちょうだいと頼むと、ライオンは『いいよ』と答えて話を始めました。ライオンはお話を聞かせながら、男の子の頭をばりばりと――」
「『ばりばり』はやめて!」とブルーノがせがんだ。「バリなんてどーでもいいでしょ――ちっちゃくてほそくて先がとがってて――」
「わかったわ、じゃあ、『ばこばこ』ね」シルヴィーが言った。「ライオンが男の子の頭をすっかりばこばこにすると、男の子は立ち去ってしまいました。『ありがとう』も言わずに!」
「ぶさほうだね」ブルーノが言った。「しゃべれないんだとしても、おじぎできるのに――そっか、おじぎのしようがないんだ。だったらライオンとあくしゅすればいいのに!」
「あら今の部分は忘れて!」シルヴィーが言った。「男の子はライオンと握手しました。だってまた戻って来たんですから。そしてお話を聞かせてくれてありがとうとライオンにお礼をしました」
「それから頭はまた生えてきたの?」
「そうよ、すぐに生えました。そしてライオンは謝って言いいました、もう男の子の頭をばこばこしません――二度といたしません!」
ブルーノは成り行きに納得したようだ。「これでほんとにいいおはなしだ! そう思わません、あなたさん?」
「ほんとうだね」ぼくは言った。「その男の子の話、もっと聞きたいな」
「ぼくも」ブルーノがまたシルヴィーの頬を撫でてねだった。「ブルーノのピクニックのはなしをしてちょうだい。ばこばこなライオンのはなしはもういいから」
「びびらせちゃったのならもうやめるわ」シルヴィーが言った。
「ちびってなんかないよ!」ブルーノは腹を立てて叫んだ。「そんなんじゃないよ! 『ばこばこな』ってのがみみざわりなことばだからだよ――ひとの肩に頭をのっけてるときにゆーことじゃないもんね。そーやって話をされるとさ――」とぼくに向かって叫んだ。「はなしてることが顔のろーがわにさがってきて――あごまでとどいて――すごくくすぐったいんだです! ひげ生えてきそうに思うくらいなんだから!」
ブルーノは鹿爪らしく口にしていたものの、冗談なのは明らかだったので、シルヴィーは笑っていた――鈴のように美しい笑い声をあげ、弟の癖っ毛のてっぺんを枕のようにして柔らかな頬を横たえたまま、シルヴィーはお話を続けた。「それでこの男の子は――」
「でもそれはぼくじゃないからね!」ブルーノが口を挟んだ。「ぼくだと思う必要はないからね、あなたさん!」
ぼくは礼儀正しく答えた。ブルーノだとは思わないようにしよう、と。
「――その男の子はわりとよい子でした――」
「とってもによい子だよ!」ブルーノが訂正した。「言われなかったことはなんにもしなくって――」
「それってよい子にしてないじゃない!」馬鹿ねぇとでもいうようにシルヴィーが言った。
「それはよい子にしてるよ!」ブルーノも言い張る。
シルヴィーが匙を投げた。「いいわ、その子はとってもよい子でした。嘘は絶対につかないし、大きな戸棚を持っていて――」
「――嘘も埃も少しもつかないように仕舞っておくためでしょ!」ブルーノが叫んだ。
「少しも嘘をつかないんだとすると」シルヴィーの目からいたずらっぽさが覗いた。「私の知ってるどの子とも似てないわね!」
「もっちろん塩を仕舞うのはもってのほかだよね」ブルーノは真剣な口ぶりだった。「塩があると、うそを漬けちゃうもんね。それからたんじょーびはどの棚にもお仕舞いにならないの」
「誕生日をお仕舞いにしないでいられるのはどのくらいのあいだなんだい?」ぼくはたずねた。「ぼくには二十四時間が限度だな」
「だってたんじょーびはほっといてもそのくらい続いているものでしょ!」ブルーノが声をあげた。「たんじょーびを仕舞わずにいる方法を知らないんだね! この子のは一年じゅーお仕舞いにならなかったよ!」
「そうしたらまた次の誕生日が始まるでしょう」シルヴィーが言った。「つまり毎日誕生日ってことじゃない」
「そうだったらなあ」とブルーノ。「あーたはたんじょー会をひらいたことある、あなたさん?」
「何回かね」ぼくは答えた。
「よい子にしてたときでしょ?」
「まあね、良い子にしてるのは素敵なことじゃないかな?」
「ステキだって!」オウム返しにブルーノが言った。「おしおきみたいなものなのに!」
「まあブルーノ!」シルヴィーは残念そうだった。「なんでそんなこと言うのよ?」
「ふん、だってそうじゃん」ブルーノも頑固だった。「ねえ、あなたさん! これがよい子だよ!」ブルーノはピンと背筋を伸ばして座り、あきれるほど生真面目な顔つきをした。「まずはマッチ箱みたいにまっすぐすわりなさい――」
「――マッチ棒みたいにまっすぐ、よ」シルヴィーが訂正した。
「――マッチ箱みたいにまっすぐとね」ブルーノはなおも言い張った。「それから手を閉じなさい――しっかりと。それから――『どうして髪をとかしてないのよ? あとからとかしておきなさい!』それから――『まあブルーノ、ひな菊を折っちゃだめよ!』。ヒナギクでつづりの勉強したことある、あなたさん?」
「その子の誕生日の話を聞きたいな」ぼくは言った。
ブルーノはすぐにお話を再開した。「うんとね、その男の子は言いました。『さあぼくのたんじょー日だ!』それから――つかれちゃったな!』ブルーノは突然話をやめて、シルヴィーの膝に頭をのせた。「シルヴィーのほうがしってるよ。ぼくより大人なんだから。つづきをおねがい、シルヴィー!」
シルヴィーは辛抱強くお話の筋を元に戻した。「そこで男の子は言いました。『さあぼくの誕生日だ。どうすれば誕生日をお仕舞いにしないでいられるんだろう?』よい子はみんな――」(ここでシルヴィーはブルーノに向かってではなく、はっきりわかるくらいの大きさでぼくにささやいた)「――よい子はみんな――きちんとお勉強する男の子は――誕生日をお仕舞いにせ…ずにいられるのです。だからもちろんこの子も自分の誕生日をお仕舞いにせ…ずにいられました」
「何ならその子のことブルーノって呼んでいいよ」男の子は素知らぬふりでそう言った。「ぼくじゃなかっても、でもその方が面白いし」
「そこでブルーノはつぶやきました。『丘のてっぺんをひとりじめしてピクニックするほどいいことはないぞ。牛乳とパンとリンゴは忘れないようにしなくちゃ。いの一番に牛乳だ!』そこでブルーノはいの一番に牛乳樽を持って――」
「牛さんのところに行って牛乳ったんだ!」ブルーノが口を挟んだ。
「そうね」シルヴィーは聞き慣れない動詞を黙って受け入れた。「すると牛は言いました。『モー! 牛乳持ってどこに行くのよ?』。ブルーノは答えました。『実はおばさん、ピクニックに持っていきたいんです』。すると牛は言いました。『モー! でも牛乳を火にかけないでくれる?』。ブルーノは答えました。『うん、するわけないよ! 新鮮な牛乳はおいしいし温かいから、火にかけなくていいもん!』」
「火にかけなくてもいいもん、だよ」ブルーノが修正案を出した。[*2]
「そこでブルーノは壜に牛乳を入れて、『次はパンだ!』と言って焼き窯のところに行き、おいしそうなできたてのパンを取り出しました。焼き窯は――」
「――とってもふかふかにふくらんだ、だよ!」ブルーノはじれったそうに訂正した。「なんでそんなにたくさんことばを抜かすのさ!」
シルヴィーは素直に謝った。「――おいしそうなできたてのパンは、とってもふかふかにふくらんでいました。焼き窯は言いました――」ここでシルヴィーは押し黙ってしまった。「焼き窯がしゃべるときに、どんな言葉から始めるのか、本当に忘れちゃったわ!」
二人の子どもが訴えるようにぼくを見た。だがぼくにはこんなことしか言えなかった。「ちっともわからないよ! 焼き窯がしゃべるのなんて聞いたことがないからね!」
しばらくぼくらは黙り込んでいた。やがてブルーノがそっと口を開いた。「やきがまは『や』の字から始まるよ」
「何ていい子なの!」シルヴィーが感嘆の声をあげた。「ブルーノは綴りがとっても得意なの。実は賢い子なんです!」とぼくに向かって耳打ちした。「そこで焼き窯は言いました。『やぁ! パンを持ってどこに行くのかな?』。ブルーノは言いました。『実はね――』。焼き窯って『おじさん』と『おばさん』どっちかしら?」シルヴィーはたずねるようにぼくを見つめた。
「どっちも、じゃないかな」そう言っておくのが一番の安全策に思えた。
シルヴィーはこの提案をすぐさま採り入れた。「そこでブルーノは言いました。『実はじばさん、ピクニックに持っていきたいんです』。焼き窯は言いました。『やぁ! だけど焼いてほしくないんだけど?』ブルーノは答えました。『うん、するわけないよ! できたてのパンはとってもふかふかふくらんでるから、焼かなくていいもん!』」
「焼かなくてもいいもん、だよ」とブルーノが言った。「省いてばっかりいないでよ!」
「そこでブルーノはパンを籠に詰めました。それから『次はリンゴだ!』と言うと、籠を持って大きな林檎の木のところまで行き、すっかり熟した林檎を摘み取りました。大きな林檎の木は言いました――」ここでふたたび押し黙ってしまった。
ブルーノは額を叩くというお得意のしのぎ方に逃げ込んだ。シルヴィーの方は真剣な面持ちで虚空をにらんでいた。まるで鳥がアドバイスしてくれることを期待しているようにも見えたが、鳥は枝にまぎれて陽気にさえずっているだけで、何も起こらなかった。
「大きな林檎の木はしゃべるとき、どんな言葉から始めるんだったかしら?」シルヴィーはなすすべもなく鳥に向かってつぶやいたが、なしのつぶてだった。
仕方がないのでぼくはブルーノのやり方を真似て口にしてみた。「『おおきな林檎の木』は『おお』から始まるんじゃないのかな?」
「ええ、もちろんそうよね! なんて頭がいいのかしら!」シルヴィーは大喜びで叫んだ。
ブルーノが飛び上がってぼくの頭をなでてくれたが、ぼくは調子に乗らないように気をつけた。
「そこで大きな林檎の木は言いました。『おお! 林檎を持ってどこに行くんだ!』。ブルーノは答えました。『実はおじさん、ピクニックに持っていきたいんです』。大きな林檎の木は言いました。『おお! だが火であぶってほしくないんだが?』。ブルーノは答えました。『うん、するわけないよ! 熟したリンゴはとってもおいしくて甘いから、あぶらなくていいもん!』」
「あぶらなくても――」とブルーノが言いかけたが、その前にシルヴィーが自分で訂正してしまった。
「『あぶらなくてもいいもん』。そこでブルーノは、パンや牛乳壜と一緒に林檎を籠に詰めました。そして丘のてっぺんへ一人きりのピクニックに出かけたのです――」
「欲ばりじゃないからさ、ひとりきりだけだったんだ」ブルーノがぼくの頬をなでてアピールした。「お兄ちゃんもお姉ちゃんもいなかったしね」
「お姉ちゃんがいないと寂しくないかい?」ぼくはたずねた。
「うーん、わかんない」ブルーノは悩ましい顔をした。「勉強しなくてすむしね。だから気が楽だし」
シルヴィーがお話を続けた。「ブルーノが道を歩いていると、後ろから聞いたこともないような音が聞こえてきました――ドン! ドン! ドン! 『何の音だろう?』とブルーノ。『あ、そうか! なんだ、ぼくの時計がチクタク鳴ってるだけじゃないか!』」
「時計がチクタク鳴ったのかな?」ブルーノがぼくに問いかけた。目にはいたずらっぽい光が輝いている。
「絶対そうさ!」とぼくが答えると、ブルーノは勝ち誇ったような笑みを浮かべた。
「それからブルーノはもうちょっと考えてみました。『ちがうぞ! 時計がチクタク鳴るもんか! だってぼくは時計を持ってないじゃないか!』」
ブルーノがぼくの顔を興味津々で覗き込んで、ぼくがどう感じているのか確かめようとした。ブルーノが大喜びしているのを見て、ぼくはうなだれて指をくわえた。
「ブルーノはさらに道を進み続けました。それでもあの不思議な音は聞こえてきます――ドン! ドン! ドン! 『何の音だろう?』とブルーノ。『あ、そうか! なんだ、大工さんがぼくの手押し車を直してくれてるだけじゃないか!』」
「大工さんが手押し車を直してたんだと思う?」ブルーノがたずねた。
ぼくは元気を取り戻して、「そうに決まってるよ!」と自信満々に答えた。
ブルーノは腕をシルヴィーの首にまわした。「シルヴィー!」と、すっかり聞こえるほどの声でささやいた。「そうに決まってるってさ!」
「それからブルーノはもうちょっと考えてみました。『ちがうぞ! 大工さんが手押し車を直してるもんか! だってぼくは手押し車を持ってないじゃないか!』」
今回ぼくは両手で顔を覆って、ブルーノの勝ち誇った顔を見なくてすむようにした
「ブルーノはさらに道を進み続けました。それでもあの不思議な音は聞こえます――ドン! ドン! ドン! 今度はそれが何なのかその目で見てやろうと、振り返ってみることに決めました。なんとそこにいたのはほかでもない、大きなライオンでした!」
「大きくでっかいライオン」とブルーノが訂正する。
「大きくでっかいライオンでした。ブルーノはびびってしまって走り出し――」
「ちがうよ、すこしもちびってないってば!」ブルーノが口を挟んだ。(同名の人物の名誉が気になって仕方ないのだ。)「ライオンをよく見ようとして走り出したんだ。だって男の子の頭をぼこぼこしてたライオンと同じかどうかたしかめたかったからさ。それにどれだけおっきいか知りたかったんだ!」
「わかったわ、ブルーノはライオンをよく見ようとして走り出しました。ライオンはそれをゆっくりと追いかけました。そしてライオンは後ろからとても優しく声を掛けました。『ぼうや、怖がらなくていいよ! おれは今じゃとても優しいライオンなんだ。昔みたいに子供の頭をぼこぼこしたりは二度としないよ』。そこでブルーノは言いました。『ホントにしないんですか? じゃあどうやって暮らしてるの?』。するとライオンは――」
「すこしもちびってないんだからね!」ブルーノはまたぼくの頬をなでた。「だって忘れずに『ですか』って言えたんだから」
その人がびびっているかどうか確かめるには確実な方法だね、とぼくは答えた。
「するとライオンは言いました。『ああ、パンとバターで暮らしているよ。それにさくらんぼ、マーマレード、レーズンケーキ――』」「――それにリンゴだ!」ブルーノが口を挟んだ。
「そうね、『それに林檎だ!』。ブルーノは訊きました。『ぼくとピクニックに行かない?』。するとライオンは答えました。『ああ、それが実は行きたくてしょうがないのだ!』というわけでブルーノとライオンは一緒に出かけましたとさ」シルヴィーが不意に話をやめた。
「これで終わりかい?」ぼくはがっかりしてたずねた。
「というわけではないんですけど」シルヴィーは茶目っ気たっぷりに答えた。「あと一、二段落くらい。そうよね、ブルーノ?」
「うん」素っ気ないのはどう見ても素振りに過ぎない。「ちょうどあと一、二段落くらい」
「二人は茂みをかき分け歩いてゆきました。そこで見たのはなんと可愛い黒羊の仔でした! 仔羊はそれはもうびびってしまって走り出し――」
「こひつじがちびったのはホントだよ!」ブルーノが口を挟む。
「走り出したので、ブルーノは追いかけて声を掛けました。『仔羊さん! このライオンは怖くないよ! えものを仕留めたりはぜったいしないんだから! さくらんぼとマーマレードで暮らしてるんだ――』」
「――それとリンゴ!」とブルーノ。「いっつもリンゴ忘れるんだから!」
「『一緒にピクニックに行かない?』とブルーノがたずねると、仔羊は答えました。『うん実は行きたくてしょうがないの、ママが行かせてくれればいいけど!』。そこでブルーノは言いました。『ママのところに行って訊いてみよう!』。というわけで、みんなで母羊のところに行き、ブルーノがたずねました。『あなたのお仔さんとピクニックに行っていい?』。すると母羊は答えました。『ええ、ちゃんとお勉強を済ませたのならね』そこで仔羊は言いました。『うんママ! 勉強はぜんぶおわったよ!』」
「ぜんぜんべんきょーしてないってことにしてよ!」とブルーノがせがんだ。
「だめよそんなの!」シルヴィーは言った。「勉強のことは譲れません! そこで母羊は言いました。『もうアルファベットはわかるの? Aは覚えた?』。仔羊は答えました。『うん、ママ! A画館に行って、A画をかんしょーしてきたの!』『いい仔ね、じゃあGは?』『うん、ママ! おGちゃんのところに行ったら、おこづかいくれたの!』『よくできたわ、じゃあKは?』『うん、ママ! K察に行って、K事さんのおてつだいしたの!』『よくできました! ブルーノとピクニックに行っていいわよ』」
「そういうわけでみんなは出かけました。ブルーノは真ん中を歩いていました。それというのも仔羊がライオンを見なくても済むように――」
「ちびってるからだよ」ブルーノが解説した。
「そうね、すごく震えていました。仔羊はどんどん顔色を失くして、丘のてっぺんに着くころには真っ白な仔羊になっていました――雪みたいに真っ白でした!」
「でもブルーノはちびってないんだよ!」名前の主が断言した。「だからブルーノは黒いままだったのです!」
「あら、そんなわけないわ! ブルーノは肌色のままだったのです!」シルヴィーが笑った。「真っ黒だったらこんなふうにキスするのはやめるわ!」
「するに決まってるさ!」ブルーノは自信満々だった。「それに、ブルーノはブルーノじゃないからね――だってさ、ブルーノはぼくじゃないから――うんとさ――へんなこと言わないでよ、シルヴィー!」
「もう言わないわ!」シルヴィーは申し訳なさそうに言った。「そうやってみんなで歩いていると、ライオンが言いました。『ああ、おれが若かったころの話をしようじゃないか。木の陰に隠れて男の子を待ってたもんさ』」(ブルーノはシルヴィーにぴったり体を寄せた。)「『やせっぽっちのガリガリの男の子ならそのまま行かせた。だが太ったみずみずしい――』」
ブルーノの我慢は限界だった。「ブルーノはひからびてるってことにしてよ!」と半べそをかきながらお願いした。
「馬鹿ねぇ、ブルーノ!」シルヴィーは明朗に答えた。「もうすぐ終わるから! 『――太ったみずみずしい男の子なら、飛びかかってがぶりと食らいついたものさ! ああ、どれだけおいしいか君にはわからないだろうな――みずみずしい男の子ときたら!』。ここでブルーノが言いました。『あの、できたらさ、男の子を食べるはなしはしないでください! ふるえちゃうから!』」
本物のブルーノも主人公に共感して震えていた。
「ライオンは言いました。『うん、それならこの話はやめにしよう! おれの結婚式の日に起こった話をしようじゃないか――』」
「そっちのほうがいいや」ブルーノは目覚ましにぼくの頬をなでた。
「『結婚記念の朝食はなんともすばらしかったよ! テーブルのこっちには大きな葡萄のプディング。あっちにはこんがり焼けた仔羊の肉! ああ、どれだけおいしいか君にはわからないだろうな――こんがり焼けた仔羊!』。ここで仔羊が言いました。『あの、お願いですけど、仔羊を食べるはなしはしないでください! ふるえがきちゃう!』。そこでライオンは答えました。『うん、それならこの話はやめにしよう!』」
Ver.1 03/08/09
Ver.2 03/08/11
Ver.3 03/09/24
Ver.4 03/11/23
Ver.5 11/04/29
[註釈]
▼*註1 [棚にお仕舞い]。この前後の一連の流れは、原文では「keep」がそれぞれ「(約束を)守る」「(戸棚に)仕舞っておく」「(誕生日を)祝う/保存する」という意味で使われています。[↑]
▼*註2 [火にかけなくても……]。原文ではシルヴィーが「it wants no boiling.」と言ったのを、ブルーノが「It doesn't want no boiling.」と「訂正」しています(意味は同じ)。もちろん文法的にはシルヴィーが正しいのですが、「not 〜 no」という表現も口語を中心によく使われる言い方です。日本語にはできませんでした……。[↑]