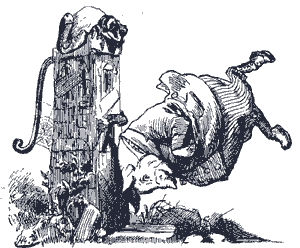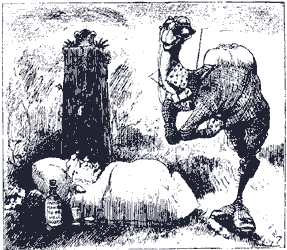この翻訳は、訳者・著者に許可を取る必要なしに、自由に複製・改変・配布・リンク等を行ってかまいません。
翻訳:東 照
ご意見・ご指摘などは
こちらまで。
シルヴィーとブルーノ完結編
ルイス・キャロル
第二十三章
豚の尾話
このころには会食者の食欲もおおむね満たされ、ブルーノでさえ、教授から四切れ目のプディングを注文されたときには「三さら寄ればもーじゅーぶん!」と言うにいたったほどだ。
突然教授が話し始めた。電気でも流されたのかと思ったほどだ。「おう、一番大事な出し物を忘れてしまうとろこじゃった! もう一人の教授が、豚のお話を暗唱いたします――つまり豚の尾話ですな」と言い直した。「始めと終わりに序詩がございます」
「終わりに序詩があるんですか?」シルヴィーがたずねた。
「まあお聞きなされ」教授が言った。「そうすればわかるじゃろうて。真ん中にもなかったとは言い切れんしの」ここで教授が立ち上がると、晩餐会場が一瞬静まり返った。みんなスピーチを待ち受けているのだ。
「お集まりの皆様」教授が切り出した。「もう一人の教授のご好意で、詩を暗唱してくださいます。題は『豚の尾話』。以前に暗唱したことはございません!」(会衆が喝采した。)「今後、暗唱する予定もございません!」(狂乱と大喝采が会場に広がり、教授は喝采に答えようと大急ぎでテーブルの上に登り、片手に眼鏡を、もう片方にスプーンを持って手を振った。)
それからもう一人の教授が立ち上がり、暗唱を始めた。
|
小鳥が食べる
人目を忍んでこそこそと、
おんぼろ部屋に身を隠し。
つまり給仕が隠した
派手な靴下――
お話することがございます。
小鳥が餌をやる
裁判官にジャムをやる、
炒めたハムをたっぷりと。
つまり牡蠣がたっぷり
暗い修道院に出没する――
言っているのはその話。
小鳥が教える
微笑み方を雌虎に、
生まれながらの悪党に。
つまり嘲笑いでなく微笑みとは――
口を半円に、
それが正しいやり方です。
小鳥が眠る
ピンに囲まれて、
そこは敗者が勝ち進む場所。
つまりくしゃみをするのはどこ
喜ぶのはいつ、どうやって――
そこで話が始まります。
|
 |
豚が一人で座っておった
壊れたポンプのかたわらで。
夜も昼もうめきをもらし――
冷たい心をかき乱す
蹄をひねってうめきをあげる、
なぜって豚は跳べないから。
とある駱駝がうめきを聞いた――
こぶが一つのひとこぶ駱駝。
「おや、悲しいのかい、痛いのかい?
どうしてそんなにわめくんだい?」
鼻を震わせ豚が答えた、
「なぜっておいらは跳べないからさ!」
夢みる目つきで駱駝は眺めた。
「思うに君は太りすぎだね。
こんなにでぶった豚は見たことない――
そんなによたよたふらふらして――
がんばったってできるもんか、
こんな恰好で跳ぶなんて!
「だがあの木立を目指したまえ、
二マイル先のあの茂みだよ。
一日二回往復すれば、
休みも遊びも我慢すれば、
遠い未来に――確信は持てぬが――
君は跳びごろサイズになるかもね」
豚を残して駱駝は去った、
壊れたポンプのかたわらに。
ああ、恐ろしきは豚の絶望!
悲しみの叫びが空気を満たす。
蹄をひねり、毛をかきむしる、
なぜって豚は跳べないから。

辺りをぶらつく蛙が一匹――
つやつや輝くかたまり発見。
魚眼でそいつを見回して、
「ねえ豚、なんで泣いてんの?」
かくも悲しきは豚の答え、
「なぜっておいらは跳べないからさ!」
蛙はにやにや喜んで、
自分の胸をバンと叩いた。
「ねえ豚、教えてやるよ、
そうしたら見たいものを見られるぜ。
さしあたり、ちっとばかし授業料をくれたら、
跳び方を教えてやるよ!
「何度も落ちて気絶するかも、
何度もぶつかり痣だらけかも。
だがしっかり耐え抜けば、
小さなことからこつこつと、
仕上げにゃ十フィートの壁も、
気づけば跳べるようになるさ!」
豚は驚き喜んだ。
「わあ蛙くん、君こそ偉人だ!
ぼくの心の痛みを癒してくれた――
さあ、授業料を言って、跳び方を教えて。
傷ついた心を慰めて
ぼくに跳び方を教えてよ!」
「授業料は羊の肉、
目標はこの壊れたポンプ。
軽やかなジャンプをご覧じろ
てっぺんまでひとっ飛び!
さあ膝を曲げてぴょんと跳ぶんだ、
なぜってそれが跳び方さ!」
豚は立ち上がり、助走をつけ、
壊れたポンプに大激突。
空っぽの袋みたいにへなへなと
背中から地面にすってんころり
途端に骨がこう言った「ピキッ!」
ああそれは死のジャンプでした。
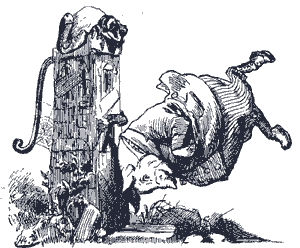
もう一人の教授は詩を暗唱しながら、暖炉に向かい、煙突に頭を突っ込んだ。そのせいでバランスを失い、火のない暖炉に頭から落っこちてしまい、そのままぴくりともしないので、引きずり出すまでしばらくかかってしまった。
だからブルーノはそのあいだにこう言った。「きっと何人くらいのひとびとたちがえんぽちにのぼってるかしりたかったんだよ」
シルヴィーが言った。「煙突よ――えんぽちじゃないわ」
ブルーノが言った。「どーでもいーよ!」
こうしているあいだにもう一人の教授が引きずり出されていた。
「顔が真っ黒であろう!」皇后が心配そうに言った。「石鹸をもってこさせようかえ?」
「いえ、結構です」顔を背けたままもう一人の教授は答えた。「黒というのは極めて高貴な色でございます。それに、石鹸とは水なしでは使えぬもので――」
もう一人の教授はうまいこと聴衆には背を向けたまま、序詩の暗唱を続けた。
|
小鳥が書く
面白い本を、
料理人に読まるために。
つまりあぶらずに読ませるために――
あぶると本文が、
台無しになるから。
小鳥が吹く
海辺でバグパイプを、
旅人たちの眠る場所で。
「ありがとう! ぞっとするよ!
ほら、お駄賃はやるから!
もうかまわないでくれ!」
小鳥が入浴する
クリーム風呂で鰐と、
幸せな夢のように。
だがそれも長くは続かないように――
鰐が断食を、
やめないともかぎらない!
|
 |
陽もかげるころ、駱駝がふらりと
壊れたポンプ辺りまで足を伸ばした。
「ああ心が痛い! 足が痛い!
大事なのは」と駱駝は言った
「もっとふわふわでほっそりすること、
じゃないと跳べないよ!」
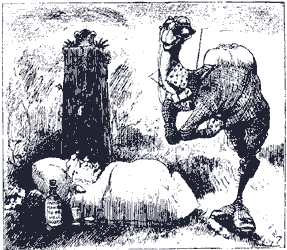
豚は石ころみたいにじっとしたまま
手足をぴくりとも動かせない。
たとえ真理がわかったところで
二度とうめきをもらさぬし
蹄をひねってうめきもあげぬ、
なぜって豚は跳べないから。
蛙は何にも言わないで
糞みたいにがっくりしていた。
どうなるかは目に見えている
授業料は手に入るまい――
悲嘆に暮れて、しゃがみ込む
壊れたポンプのてっぺんで!

「ひげきてきなおはなし! ひげきてきにはじまって、もっとひげきてきにおわっちゃった。泣いちゃいそう。シルヴィーのハンカチかしてよ」
「持ってないわ」シルヴィーは小声で答えた。
「なら泣かない」ブルーノは男らしく返答した。
「まだ序詩はございますが」もう一人の教授が言った。「しかしながら腹が減りました」腰を下ろすとケーキを一切れ大きく切り出し、ブルーノの皿にのせると、自分の空っぽの皿を驚いて見つめていた。
「そのケーキどこから持ってきたの?」シルヴィーがブルーノにささやいた。
「もーひとりのきょーじゅがくれたんだ」
「でもあなた頼んでないじゃない! そんなのわかってるでしょう!」
「たのんでないけど」ブルーノはケーキを口に頬張ったまま答えた。「くれたんだもん」
シルヴィーはしばらく考えてから、どうすればいいかひらめいたらしい。「ふうん、じゃあ私にくれるように頼んでよ!」
「ケーキを堪能しとるようじゃな?」教授が言った。
「それ『食べる』って意味?」ブルーノはシルヴィーにささやいた。
シルヴィーはうなずく。「『食べる』とか『おいしくいただっく』って意味よ」
ブルーノは教授に微笑んだ。「たんのーしてるよ」
その言葉をもう一人の教授が聞きつけた。「おぬしは口も堪能のようじゃのう?」
ブルーノはびっくりして恐ろしげな目つきを返した。「ううん、そんなわけないじゃん!」
もう一人の教授はすっかり弱り切ってしまい、「まあええ、まあええ! 桜草のワインはどうじゃ!」と言って、グラス一杯に注いでブルーノに差し出した。「飲んでみなされ、別人になったような気分じゃぞ!」
「誰になるの?」ブルーノはグラスに唇を押しつけたままためらった。
「質問ばっかりしないの!」シルヴィーが割って入り、哀れな老人を混乱の極致から救おうと試みた。「教授にお話を聞かせてもらいましょう」
ブルーノはその考えに飛びつき、「おねがい!」とせがんだ。「トラのおはなし――それと、ぶんぶんミツバチ――それと、コマドリ、ね!」
「なぜいつも生き物の話ばかりなんじゃ?」教授が言った。「事件とか出来事の話ではいかんのか?」
「だったらおねがい、そーゆーおはなしを考えてよ!」
教授はすらすらと話し始めた。「むかしむかし、偶然が些細な事件と散歩しておった。で、二人は解釈と出会った――たいそう古い解釈じゃ――あまりに古かったので完全に分裂し、ほとんど謎々みたいに見えた――」教授は突然、話をやめた。
「おねがい、つづけて!」子どもたちが大声で訴えた。
教授は率直に打ちあけた。「話を考えるというのはたいそう難しいことじゃの。まずブルーノが聞かせてくれんか」
ブルーノは大喜びでこの申し出を受け入れた。
「むかしむかし、ブタとアコーディオンとオレンジ・マーマレードのビンが二ついました――」
「それが配役じゃな」教授がつぶやいた。「ふむ、それから?」
「それで、ブタがアコーディオンをひいていました」ブルーノは続けた。「片方のオレンジ・マーマレードのビンは、その曲がきらいでした。もう片方のオレンジ・マーマレードのビンは、その曲がすきでした――ねえシルヴィー、ぼくぜったいにオレンジ・マーマレードのビンがごっちゃになっちゃいそう!」ブルーノは不安そうにささやいた。
「さて残りの序詩を暗唱させていただきましょう」もう一人の教授が言った。
|
小鳥が窒息させる
准男爵にパンを詰めて、
射撃を教えた准男爵を。
つまり教えてくれたのは
冬場の鮭の刻み方――
それもただの道楽で。
小鳥が隠す
旅行鞄に罪の証拠を隠す、
幸せな牡鹿に祝福された鞄に。
つまり祝福されたのにぶたれるのは――
友人たちが食べられるから
名声が衰えると。
小鳥が味わう
感謝の気持ちと黄金を、
急な寒さに青ざめた。
つまり青ざめ、しわ寄せ――
ベルが鳴らされ、
お話が始まります。
|
 |
「続きましては」豚の尾話への喝采が終わるとすぐに、教授は嬉々として長官に話しかけた。「皇帝陛下の健康を祝して乾杯でしょうな?」
「さようである!」長官は厳かに答え、立ち上がって儀式をおこなうために号令をかけた。「皆さんグラスをお満たし下さい!」という大音声に、誰もがすぐにしたがった。「皇帝陛下の健康を祝して乾杯!」グラスを空ける音が広間にこだました。「皇帝陛下に万歳三唱!」このかけ声を合図に、気絶せんばかりの大声が轟いた。それが終わるとすぐに、長官は驚くほど冷静に発表した。「皇帝陛下のお言葉であーる!」
その言葉が発せられる間もあらば、皇帝は演説を始めていた。「皇帝になるのは嫌じゃったが――皇帝になることを諸君が望んだわけじゃから――知っての通り先の総督がやっておったことはひどいもので――諸君が見せてくれたような熱意で――総督は諸君を迫害しておった――重すぎる税を課し――誰が皇帝にふさわしいか諸君は知っておったわけじゃ――我が兄は判断力がなく――」
この珍妙な演説がいつまで続くはずだったのかはお伝えできない。なぜならちょうどそのとき一陣の嵐が宮殿を土台から揺るがしたため、音を立てて窓がバタンと開き、明かりがいくつか消え、埃が宙にもうもうと立ち込めて奇妙な形を取ったが、それはどうやら文字を形作っているようだった。
だが嵐は起こったときと同じく不意に止んだ――窓はふたたび元の場所に収まり、埃も消えていた。すべてが一分前と何ら変わりはなかった――ただし皇帝と皇后だけは別で、この二人には驚くべき変化が訪れていた。空虚な眼差し、無意味な笑みは姿を消していた。この見慣れぬ二体の存在が正気を取り戻したのは誰の目にも明らかだった。
皇帝は何の邪魔も入らなかったかのごとく演説を続けていた。「そして我々は行動いたしました――妻と私は――根っからの悪党のように。ほかの表現など見あたりません。兄が去ったとき、諸君は過去最高の総督を失った。私は皇帝になるため諸君を騙すことに全力を尽くしてきた、浅ましい偽善者だ。この私が! 靴磨きになる知恵すらないというのに!」
長官が絶望して両手を揉み合わせた。「陛下は狂気に見舞われたのだ、諸君!」長官も口を開いたが、二人の演説は突然やんだ――そして、死んだような静寂のあとに、ドアを叩く音が聞こえた。
「何なんだ?」人々は叫んで、行ったり来たりし始めた。徐々に興奮してきた長官が、宮廷作法などすっかり忘れて、全速力で広間を走り抜け、すぐに戻ってきたときには真っ青になって息を切らしていた。
Lewis Carroll "Sylvie and Bluno Concluded" -- Chapter XXIII 'The Pig-Tale' の全訳です。
Ver.1 03/09/10
Ver.2 03/11/16
Ver.3 11/07/04
[註釈]
▼*註1 []。[↑]