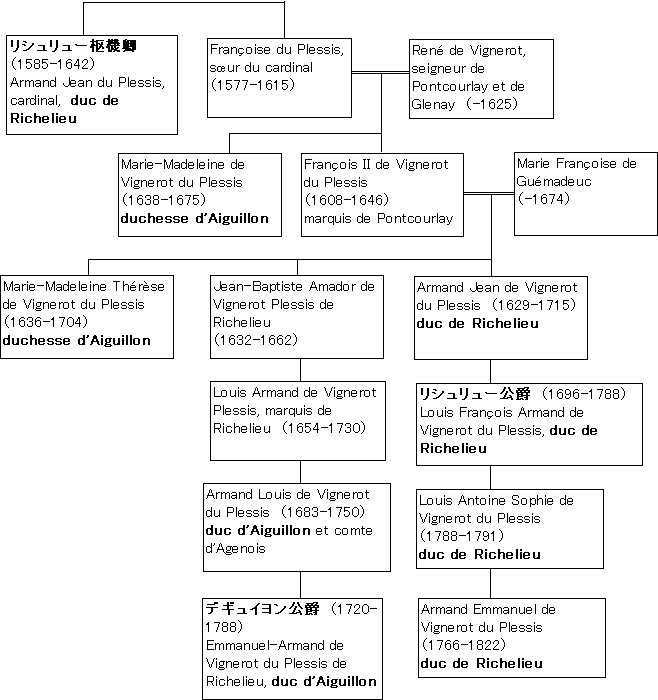 図をクリックで拡大。
図をクリックで拡大。パリやシャントルーの路上で待っていたのが顔をしかめて目を腫らした人間であったように、リュシエンヌにもたらされたのは、顔をほころばせた魅力的な笑顔であった。
今やリュシエンヌの玉座についているのは一介の人間ではない。宮廷人や詩人の言うようなあらゆる人間の内でもっとも美しく可憐な人間ではなく、フランスを統治しているのは紛れもない神であった。
そういうわけだからド・ショワズール氏が罷免されたその日、朝は大臣の四輪馬車を追っていたお供の者たちが、夕方になっても路上を埋め尽くしていた。さらには高官や賄賂や贔屓を愛する者たちが大きな列を成しているのが見えた。
だがデュ・バリー夫人には独自の捜査機関がある。ジャンはショワズール兄妹に向かって最後の花を投げようとしていた人々の名前を、有力者は別にしてだが手に入れ、伯爵夫人に伝えた。名前を告げられた者たちは一掃され、輿論に立ち向かう勇気を持っていた者たちが、その日の女神のいたわるような微笑みとこのうえない眼差しを賜った。
馬車の行列と人混みの後には、個人的な接見が待っていた。この日の隠れた主人公であるリシュリューは、来訪者や請願者が押し寄せるのを尻目に、閨房の奥に引っ込んだ。
人が喜び合ったように、神は喜びを知っていた。握手に次ぐ握手、押し殺した笑い声を洩らし、昂奮から足を踏み鳴らす、それがリュシエンヌの住人たちの日常になったかのようであった。
「忌憚なく申しますと、ド・バルサモ伯爵でもド・フェニックス伯爵でもどちらでも構いませんけれど、あの人こそ当代の第一人者じゃありませんの。いまだに魔法使いを火あぶりにするなんて残念でなりません」伯爵夫人が言った。
「まさしく、たいした人物です」リシュリューが答えた。
「おまけにちょっといい男で。ぐっと来るじゃありませんの……」
「妬けますなあ」リシュリューはからからと笑ったものの、急いで真面目な話に舵を切った。「……フェニックス伯爵なら恐るべき警察大臣になれるでしょうな」
「そのことは考えてみましたけれど、無理ですわ」
「何故です?」
「同僚がいるところが考えられませんもの」
「はて?」
「すべてお見通しで、手の内のカードを見透かせるんですから……」
リシュリューは頬紅の下で顔を赤らめた。
「伯爵夫人、わしが同僚なら、永遠に手の届くところに置いておきたいし、カードの中身を知らせてもらいたいところですな。ハートのジャックがクイーンの膝許やキングの足許に額ずいているのがいつでも確認できるのですから」
「あなたほど抜け目のない方はちょっといませんわね。でもそれより大臣のポストのことなんですけれど……甥御さんに事前に知らせていたはずだと記憶してましたけど……?」
「デギヨンですか? 到着いたしましたぞ。それもローマの占い師なら吉祥だと判ずるような状況で。ショワズール氏の馬車が出るところに居合わせたのです」
「まさに吉祥ね。それで、ここにはいらっしゃるの?」
「デギヨン殿がこんな時期にリュシエンヌにいるのを見られては、どんな噂が立つとも限りません。わしから連絡が行くまでは、村でじっとしていろと頼んでおきました」
「ではすぐに知らせて下さいな。ここにいるのはあたくしたちだけみたいなものですもの」
「喜んで。それにしても話が合いますな」
「ほんとうに……ところで……財務総監より陸軍大臣の方がお好きかしら? それとも海軍の方が?」
「陸軍の方がよいですな。その方がお役に立てるでしょうから」
「仰る通りね。その旨を陛下にお伝えしておくわ。お嫌ではありませんよね?」
「何をです?」
「陛下がお選びになる同僚のことです」
「わしは気難しい人間ではありませんぞ。だがそれより甥を呼んでも構わぬでしょうな、何せ謁見の栄誉をお許し下さるのですから」
リシュリューは窓に近寄った。日没の残光が中庭を照らしている。窓際に控えていた従僕に合図を送ると、すぐに駆け出して行った。
そうしているうちに、伯爵夫人の部屋に明かりが灯された。
従僕が出ていってから十分後、馬車が第一中庭に乗り入れられた。伯爵夫人が窓に目をさっと向けた。
リシュリューはそれを見逃さなかった。デギヨン氏にとって、ひいては自分自身にとっていい兆候だ。
――伯爵夫人は伯父を気に入ってくれておる。甥にも好意を持っておる。わしらはここで支配者になれそうだ。[*1]
そんな物思いに耽っていると、戸口で小さく物音がして、腹心の従者がデギヨン公爵の訪いを告げた。
洗練された魅力的な貴族にして、身なりは豪華なだけでなく無論上品でもあった。デギヨン氏は若々しい盛りをとうに過ぎていたが、目つきと意思の力によって、老いてなお若さを保っている類の人間であった。
たとい政治的な不安を抱いているにせよ、額には深い溝は刻まれてない。政治家や詩人が偉大な思想を温めているような、さり気ない皺が広がっているだけだった。真っ直ぐに上げた顔には、鋭さと憂いが浮かんでいた。それはあたかも何万人もの憎しみにのしかかられているのを自覚していながらも、それに負けるわけがないことを証明しようとしているかのようであった。
デギヨン氏はひどく美しい手をしていた。レースの中に紛れていても遜色がないほど白く細やかな手である。当時は形の良い足が高く評価されていた。デギヨン公爵の足は気品溢れる筋肉と貴族的な形状の見本であった。公爵には詩人のかぐわしさ、貴族の気高さ、銃士のしなやかさがあった。伯爵夫人にとってそれは理想が三つ重ねられたようなものだった。一つの理想の中に、本能的に惹かれざるを得ないような三つのタイプを見出したのだ。
驚くべき奇遇によって、もとい状況判断に基づいてデギヨン氏が立てた戦術によって、世間から厳しい目を向けられているこの二人の男女は、輝かしい状況でこれまで顔を合わせたこことはなかった。
事実三年前からデギヨン氏はブルターニュで忙しくしているか自室にいるかのどちらかだった。好不都合にかかわらずそのうち難しい事態が生ずることを見越して、宮廷にはほとんど顔を出さなかった。好都合なことが起こった場合、領民に贈り物をするなら見知らぬ者からの方がよい。不都合なことが起こったなら、ほとんど跡を残さず姿を消し、そのうちまた新たな顔をして深淵から抜け出た方がよい。
さらにはこうした計算の内には、もう一つ大きな理由が働いていた。それは物語じみた心の動きではあったが、にもかかわらず何よりも大きな理由であった。
デュ・バリー夫人は伯爵夫人になって夜毎フランスの王冠に口づけするようになる前には、笑顔に溢れた惚れ惚れするような美しい女性であった。愛されていたし、幸せだった。恐れを覚えて以来、もはや幸せに期待をかけることはなくなったが。
若く豊かで力も美も備えた男たちから、ジャンヌ・ヴォベルニエは口説かれていた。三流詩人たちが、ランジュと
こういう次第で、デギヨンが急にいなくなってもデュ・バリー夫人は初めの内ほとんど気にしなかった。過去を恐れていたせいもある。だがやがて、かつての崇拝者が沈黙を守っているのを見て、不思議がり、次いで驚愕し、これが男の評価時だと気づいてからは、デギヨンのことを頭の切れる男だと評価した。
伯爵夫人にしてみればこれは大変な讃辞である。だがそれだけに留まらない。機会さえあれば優しい男だと評価を下したことだろう。
ランジュ嬢には過去を恐れるだけの理由があったと言わざるを得ない。かつて恋人だった銃士が、ランジュ嬢の愛情や言葉を取り戻したがって、ある日ヴェルサイユにまでやって来た。かつての睦言は今や王国の気高さによって早々と息の根を止められ、それでもなお、ド・マントノン夫人の口から控えめな噂が流れて来るのは避けられなかった。
これまで見て来たように、リシュリュー元帥はデュ・バリー夫人との会話を通して、甥とランジュ嬢との関係には一切触れなかった。難しい問題を口にするのに慣れている老公爵のような人間が口を閉ざしているの見て、伯爵夫人はひどく驚いていたし、もっと言うなら不安に駆られていると言わざるを得なかった。
そういうわけだから、伯爵夫人はどう振る舞うべきかわからず、苛々しながらデギヨン氏を待っていた。一方の元帥は控えめというよりは知らんぷりを決め込んでいたと言うべきだろうか。
デギヨン公爵が姿を見せた。
王妃に対するのでも廷臣の妻に対するのでもない恭しい挨拶を、怯まず悠々とやってのけたので、その微妙な違いに気づいた伯爵夫人はすっかり魅了され、極めて申し分ない気持にされた。
続いてデギヨン氏が伯父の手を取ると、伯父は伯爵夫人に近づいて麗しい声を出した。
「こちらがデギヨン公爵です。わしの甥ではなく、あなたのために尽くす人間です。これほど誠実な人間をご紹介できることを光栄に思います」
伯爵夫人はその言葉を聞いてデギヨン公を見つめた。女を見つめるように、つまり何者も逃れることの出来ないような目つきで見つめた。伯爵夫人には恭しく下げられた二つの顔しか見えていなかった。挨拶を済ませて穏やかに上げられた二つの顔しか見えていなかった。
「あなたが公爵殿を可愛がってらっしゃるのはわかってますわ、元帥閣下。あなたはあたくしの友人です。ですから公爵閣下、伯父さまに敬意を表して、伯父さまがあたくしにして下さるように尽くして下さることをお願いいたします」
「言われるまでもなくそうして参りました」デギヨン公爵はそう言って再びお辞儀をした。
「ブルターニュでは随分と苦労なさったんでしょう?」
「ええ、しかもまだ終わっておりません」
「そうではないかと思ってました。でもこちらにいらっしゃるド・リシュリュー閣下が手を貸して下さいますわ」
デギヨンは驚いたようにリシュリューを見つめた。
「あら、まだお二人でお話しする暇がなかったのね。当たり前ね、旅から戻ったばかりなんですもの。お話ししたいことは山ほどおありでしょうね、お先に失礼しますわ、元帥閣下。公爵殿、ここがあなたのお部屋です」
伯爵夫人はその言葉を残して立ち去った。
だが伯爵夫人には計画があった。遠くには行かずに、閨房の後ろにある大きな
だからデュ・バリー夫人はリシュリュー公と甥の会話をすっかり盗み聞き出来るものと信じていた。甥について最終的な判断を下すつもりだったのだ。
だがリシュリュー公は騙されなかった。王室や内閣の秘密なら大部分を把握していたのである。人が話をしている時には耳を傾けるのが公爵の戦術であり、人が話を聞いている時には口を開くのが策略であった。
そこでデュ・バリー夫人がデギヨンに配慮を見せた際、その鉱脈を最後まで突き進もうと決意した。寵姫が不在を装っているのを利用して、秘密という小さな幸運と陰謀という大きく厄介な力を差し出してやろうと決意した。女なら、それも宮廷の女とあらば、この二つの餌には抵抗できぬだろう。
リシュリュー公はデギヨン公を坐らせて話しかけた。
「わかるな、わしはここで一廉の地位を得ておる」
「ええ、わかります」
「あの方の寵愛を得ることが出来た。ここでは王妃扱いされてらっしゃるし、事実上王妃じゃな」
デギヨンが頭を下げた。
「よいか、道の真ん中でこんなことを言うわけにはいかぬが、実はデュ・バリー夫人はわしに大臣の椅子を約束してくれた」
「まあ当然でしょうね」
「当然かどうかはわからぬが、そうなった。遅ればせながらではあるが。大臣になった暁には、お前のために世話してやるつもりだ、デギヨン」
「ありがとうございます。持つべきものは親戚だ、一度ならず助かってます」
「何かなりたいものはないのか?」
「公爵と貴族の肩書きを剥奪されなければ、特に何もありませんね。高等法院の連中は、その剥奪を要求していますが」
「何処かに支持者はいないのか?」
「私の支持者ですか? 一人も」
「ではこういう状況にならなければ、破滅していたのではないか?」
「ぺしゃんこでしたね」
「ううむ! それにしても哲学者のような話し方を……要するに、わしがきつい言い方をするのはそのせいなのだぞ、デギヨンよ。伯父としてではなく大臣として話しているのだ」
「伯父上、あなたのご親切には感謝の気持で一杯ですよ」
「わしがお前を大急ぎで呼び寄せたのは、ここで立派な役を演じさせたいからだということくらいわかるであろう……ショワズール氏が十年間演じて来た役のことを、少しでも考えたことはあるのか?」
「ええ、確かに立派な人でしたね」
「立派だと! ポンパドゥール夫人と協力して国王を操り、イエズス会士を追放させた頃は、確かに立派だった。だが悲しいかな、ポンパドゥールの百倍も素晴らしいデュ・バリー夫人と愚かにも仲違いして、二十四時間後には追放されてしまったのは、お粗末と言うほかない……何も言うことはないのか」
「聞いていますよ、何を仰りたいのか考えていたのです」
「ショワズールの最初の役どころは、いいとは思わんかね?」
「それはそうです。居心地がいいでしょうね」
「要するに、わしが演じようと決めたのはその役なのだ」
デギヨンはぎょっとして伯父を見つめた。
「正気ですか?」
「当たり前だ。何故いかん?」
「デュ・バリー夫人の愛人になるおつもりですか?」
「いやはや、先走りおって。まあしかし、わしの言うことは理解しておるようだな。確かにショワズールは幸運だった。国王を操り、寵姫を操っていた。ポンパドゥール夫人を愛しているという噂もあった……それはそうと、何故いかん?……いや、その通り。わしは魅力的な愛人にはなれん。その薄ら笑いで言いたいことはわかる。その若々しい目で、わしの皺の寄った額、曲がった膝、干涸らびた手を見るがいい。昔は綺麗だったのだが。ショワズールの話に戻るが、『わしが演じる』ではなく、『わしらが演じる』と言うべきだったな」
「伯父上!」
「わしに愛人の資格がないことくらいはわかっておる。だが話しておこう……構わん。本人に知られることはないのだから。わしは誰よりもあの方を愛していたはずだ……だが……」
デギヨンが眉を寄せた。
「だが、素晴らしい計画を考えたのだ。わしの年で不可能であるのなら、この役を二つに分ければよい」
「おお!」
「わしの身内の誰かがデュ・バリー夫人を愛する……素晴らしいことだ……完璧な女性を」
リシュリューは声を大きくした。
「フロンサックは無理として、白痴、馬鹿、臆病者、悪戯小僧、百姓……さあ何になりたい?」[*2]
「気が狂ったのですか?」
「気が狂った? 助言している人間の足許からもうはやいなくなったらしいな! 喜びにとろけ、感謝に燃えてはおらぬのか! 伯爵夫人のもてなし方を見ても、心を奪われぬのか?……恋に落ちぬのか?……よかろう、アルキビアデス以来この世にリシュリューは一人しかおらなんだ、今後は一人もいなくなるのだろう……ようわかった」
「伯父上」デギヨン公爵が、たとい見せかけにせよ、動揺してみせた。見せかけだとするならば見事な出来栄えだったが、急な申し出だったことを鑑みれば演技ではなかったのかもしれない。「あなたが仰った役割から何をどう利用しようとしているのかすっかりわかりましたよ。あなたはショワズール氏の権威を借りて支配し、私は愛人になってその権威を支えるというわけですね。いいでしょう、フランス一の智恵者らしい計画だ。ただしことに当たっては一つだけ覚えておいて下さい」
「どういうことだ……?」リシュリューが顔を曇らせた。「デュ・バリー夫人を愛さぬということか? そうなのか?……馬鹿者が! 底抜けの馬鹿めが! 何てことだ! そうなのか?」
「そういうことではありませんよ」言葉の一つとしておろそかにされるべきではないと承知している口振りだった。「デュ・バリー夫人にはお会いしたばかりですが、あれほど美しく魅力的なご婦人はいないでしょう。むしろ狂おしいほど愛してしまうでしょうし、愛し過ぎてしまいそうです。問題はそこではありません」
「では何が問題なのだ?」
「問題は、デュ・バリー夫人が愛してくれそうにないことですよ。こうした同盟の第一条件は愛ですからね。こんなきらびやかな宮廷の中で、ありとあらゆる素晴らしさに満ちた若者たちの中から、私のことを高く買ってくれるとお思いですか? 何の取り柄もなく、もはや若くもなく悲しみに打ちひしがれ、来たるべき死を覚悟して目を伏せているような人間を? 伯父上、まだ若く輝いていた頃にデュ・バリー夫人に出会っていたなら、ご婦人たちが若さの魅力のすべてを私に見出し愛してくれた頃なら、伯爵夫人も記憶に留めておいてくれたでしょう。そうであればどれほどよかったか。だが無理ですね……過去も、現在も、未来も。伯父上、そんな空想は捨てなければなりません。うっとりするほど輝く伯爵夫人に引き合わせて、私の心を突き刺したに過ぎないんですよ」
モレが羨み、ルカンが見習うような、情熱的な長台詞が辯ぜられている間、リシュリューは口唇を咬んで呟いていた。[*3]
――こやつは伯爵夫人が聴いていることに気づいておるのか? たいした奴だ! 名人芸だな。だとすると、用心せねば!
リシュリューは正しかった。伯爵夫人は耳を澄まし、デギヨンの言葉の一つ一つを心に染み渡らせていた。告白の呪文をしっかりと味わいながら飲み干し、きめ細やかな風味を楽しんだ。内なる自分に問い合わせてみても、かつての恋人の思い出を裏切りはしなかった。或いはまだ心を残している肖像に影を落とすのを恐れてのことだったかもしれない。
「では、断るのか?」リシュリューがたずねた。
「その点については仰る通りです。生憎ですが不可能に思えますから」
「せめて試してみぬか?」
「どのように?」
「わしらとここにいれば……伯爵夫人に毎日会える。気を引いてみればよい!」
「手前勝手な目的のためにですか?……お断りだ!……そんなえげつない思いで気を引くくらいなら、世界の果てまで逃げ出した方がましですね。私にも恥というものがある」
リシュリューがまた顎を掻いた。
「賽は投げられたのだ。それともデギヨンは馬鹿なのか」
ここで突然、中庭に音がして、声が張り上げられるのが聞こえた。「国王陛下です!」
「これはしたり! 国王とここで顔を合わせるわけにはいかぬ。わしは退散するとしよう」
「では私は?」
「それはまた別だ。会わなくてはならぬ。このまま……ここに……間違っても引いてはならぬぞ」
そう言ってリシュリューは階段を通って姿を消した。
「では明日!」
Alexandre Dumas『Joseph Balsamo』Chapitre LXXXVII「M. le duc d'Aiguillon」の全訳です。
Ver.1 11/02/12
Ver.2 19/02/20
[註釈・メモなど]
・メモ
▼「大蔵陸軍卿」。la Guerre aux Finances。「la Guerre」は「陸軍省(大臣)/国防省(大臣)」ですが、後ろに「aux Finances」がくっついているのがわかりません。 →「Vous préférez… la Guerre aux Finances, 」なので、「préférer à」ですよね、「財務総監より陸軍大臣の方がお好きかしら?」に訂正。
▼1770年当時、リシュリューは74歳、デギヨンは50歳。
▼「ジャンヌ・ヴォベルニエ」「ランジュ嬢」。ともにデュ・バリー夫人のこと。
・註釈
▼*1. [伯父/甥]。今さらながら「叔父」か「伯父」かが気になったので系図を確認。[↑]
▼*2. [フロンサック]。duc de Fronsac。リシュリュー家の相続人に与えられる爵位。デギヨン家の人間には資格がない。[↑]
▼*3. [モレが羨み、ルカンが……]。モレ(François Molé)、ルカン(Lekain)、いずれも18世紀のフランスの俳優。[↑]